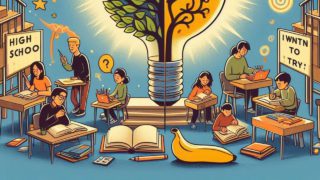オンライン面接でどう見抜く?画面越しでも伝わる、生徒の探究への熱量と主体性
コロナ禍を経て、大学入試のオンライン面接は急速に普及しました。しかし多くの入試担当者から「画面越しでは生徒の本当の姿が見えない」「探究への熱量や主体性をどう評価すればよいのか」という声が聞かれます。対面とは異なる環境で、生徒の本質をどのように見抜けばよいのでしょうか。本記事では、オンライン面接特有の課題を踏まえながら、生徒の探究への真の熱意と主体性を見極める具体的な手法を解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
オンライン面接の現状と課題
文部科学省の調査によると、2024年度入試では約70%の大学がオンライン面接を実施しており、今後もこの傾向は続くと予想されています。しかし、オンライン面接には対面にはない独特の課題があります。
対面との違いがもたらす評価の難しさ
対面面接では、生徒の全身の動きや細かな表情の変化、場の空気感など、非言語的な情報を総合的に捉えることができます。一方、オンライン面接では以下のような制約があります。
- カメラの画角による視覚情報の限定
- 音声の遅延やノイズによるコミュニケーションの齟齬
- 画面の解像度による表情の読み取りづらさ
- 場の雰囲気や緊張感の伝わりにくさ
生徒側の環境格差という新たな問題
また、生徒の自宅環境や通信環境の差が、評価に影響を与える可能性も無視できません。安定した通信環境や静かな面接スペースを確保できない生徒が、不利にならないような配慮も必要です。
探究への熱量を見抜く5つの質問テクニック
オンライン面接でも、適切な質問設計により、生徒の探究への熱量を見抜くことは可能です。以下、効果的な質問テクニックを紹介します。
1. プロセスを深掘りする「Why」の連鎖
「なぜその探究テーマを選んだのですか?」という基本的な質問から始め、回答に対してさらに「なぜ」を重ねていきます。
- 「なぜその課題に興味を持ったのですか?」
- 「その問題意識はどのような経験から生まれましたか?」
- 「他のアプローチではなく、なぜその方法を選んだのですか?」
表面的な回答では答えられない深い部分まで掘り下げることで、本当の動機や熱意が見えてきます。
2. 困難や失敗に対する向き合い方を問う
探究活動における困難や失敗をどう乗り越えたかを具体的に聞くことで、粘り強さと主体性を評価できます。
- 「探究の過程で最も困難だったことは何ですか?」
- 「失敗から学んだことを具体的に教えてください」
- 「計画通りに進まなかったとき、どのように対処しましたか?」
3. 具体的なエピソードを引き出す
抽象的な説明ではなく、具体的な場面や行動を語ってもらうことで、実際の取り組みの深さが見えてきます。
- 「印象に残っている具体的な調査場面を教えてください」
- 「データ収集で工夫した点を具体例を挙げて説明してください」
- 「チームメンバーとの意見の相違をどう解決しましたか?」
4. 探究の「その後」を問う
探究活動が終わった後も継続的に関心を持っているかを確認することで、本物の熱量を測ることができます。
- 「探究活動後も、そのテーマについて追求していることはありますか?」
- 「もし時間があれば、さらに深めたい点はありますか?」
- 「この探究が、あなたの日常生活にどんな影響を与えましたか?」
5. 画面共有を活用した実演型質問
オンライン面接の利点を活かし、画面共有機能を使って成果物や資料を見せてもらいながら説明を求めます。
- 「作成した資料を画面共有しながら、工夫した点を説明してください」
- 「データの分析過程を、実際の画面を見せながら解説してください」
- 「最も苦労した部分を、具体的に示しながら説明してください」
主体性を評価するための観察ポイント
オンライン面接でも、以下の点に注目することで生徒の主体性を評価できます。
回答の自発性と具体性
自分の言葉で語れているかは重要な指標です。暗記した内容を話すのではなく、自分の経験や考えを自然に表現できる生徒は、主体的に探究に取り組んできた可能性が高いです。
質問への反応速度と柔軟性
予想外の質問に対して、考えながら誠実に答えようとする姿勢は、主体性の表れです。完璧な回答よりも、思考過程が見える回答の方が価値があります。
探究内容への愛着と継続性
探究テーマについて語るときの表情の変化や声のトーンは、画面越しでも伝わります。本当に興味を持って取り組んだ生徒は、自然と熱を帯びた語り口になります。
失敗や困難を語る姿勢
成功体験だけでなく、失敗や困難も含めて語れる生徒は、主体的に課題に向き合ってきた証拠です。失敗を隠さず、学びとして昇華できているかを見ます。
Study Valley TimeTactによる解決アプローチ
オンライン面接での評価の質を高めるために、Study Valley TimeTactは以下のような機能で大学をサポートします。
探究活動の詳細な記録による事前情報の充実
TimeTactでは、生徒の探究活動の全プロセスが時系列で記録されています。面接官は事前にこれらの情報を確認することで、より深い質問を準備できます。
- 探究テーマの変遷と深化の過程
- 調査・実験の詳細な記録
- 振り返りと改善のサイクル
- 指導教員からのフィードバック履歴
デジタルポートフォリオを活用した実証的な評価
生徒は自身のデジタルポートフォリオを画面共有しながら、具体的な成果物や活動記録を示すことができます。これにより、口頭説明だけでは伝わりにくい探究の深さを可視化できます。
評価ルーブリックの標準化とトレーニング
TimeTactは、オンライン面接に特化した評価ルーブリックのテンプレートを提供。また、面接官向けのトレーニングコンテンツも充実しており、評価の質と公平性を担保します。
面接録画とレビュー機能
面接の様子を録画し、複数の評価者で事後レビューすることが可能です。これにより、見逃しがちな生徒の反応や発言を再確認でき、より公正な評価につながります。
まとめ
オンライン面接での生徒評価は、確かに対面とは異なる難しさがあります。しかし、適切な質問設計と観察ポイントの理解により、画面越しでも生徒の探究への熱量と主体性を見抜くことは十分可能です。
重要なのは、オンラインの制約を嘆くのではなく、その特性を理解した上で新しい評価手法を確立することです。画面共有機能の活用やデジタルポートフォリオの参照など、オンラインならではの利点も積極的に活用していくべきでしょう。
Study Valley TimeTactのようなツールを活用することで、生徒の探究活動の全体像を把握し、面接での限られた時間でも本質的な評価が可能になります。これからの大学入試において、オンライン面接の質を高めることは、優秀な人材を見逃さないためにも極めて重要な課題といえるでしょう。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。