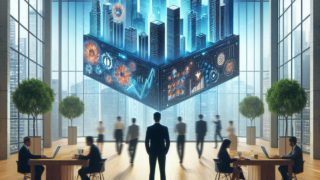非認知能力は評価できるのか?探究活動から見る「粘り強さ」と「協働性」
大学入試改革が進む中、多くの大学が学力試験では測れない「非認知能力」の評価に注目しています。特に、困難に直面しても諦めない「粘り強さ」や、他者と協力して成果を生み出す「協働性」は、大学での学びや社会での活躍に不可欠な能力です。しかし、これらの能力を客観的に評価することは容易ではありません。本記事では、探究活動を通じて非認知能力をどのように見極めることができるのか、具体的な評価方法と注意点について解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
非認知能力への注目が高まる背景
なぜ今、大学入試において非認知能力の評価が重要視されているのでしょうか。文部科学省の調査(2024年)によると、大学中退者の主な理由の上位に「学習意欲の喪失」「人間関係の構築困難」が挙げられています。これは、学力だけでは大学生活を成功させることが難しいことを示しています。
社会が求める人材像の変化
また、経済産業省の「人材力強化に向けた研究会」報告書(2023年)では、企業が新卒採用で重視する能力として以下が挙げられています。
- 主体性(89.2%):自ら考え行動する力
- 実行力(85.6%):目標に向かって粘り強く取り組む力
- チームワーク(82.3%):多様な人々と協働する力
- 課題発見力(78.9%):現状を分析し問題を見つける力
- 柔軟性(75.4%):意見の違いを理解し受け入れる力
これらの能力は、従来の学力試験では測定が困難な非認知能力に該当します。
探究活動が評価の場として注目される理由
探究活動は、生徒が長期間にわたって主体的に取り組む活動であり、その過程で様々な非認知能力が発揮されます。単発のテストや面接では見えない、本来の資質や能力が表れやすいのです。
「粘り強さ」を探究活動から評価する方法
「粘り強さ」は、困難や失敗に直面しても諦めずに目標に向かって努力を続ける能力です。探究活動において、この能力をどのように見極めることができるでしょうか。
1. 困難への対処プロセスに注目する
探究活動では必ず壁にぶつかる瞬間があります。その時の対処方法から粘り強さを評価できます。
評価ポイント:
- 最初の計画が失敗した時、どのように方向転換したか
- データ収集がうまくいかない時、どんな代替案を考えたか
- 予想と異なる結果が出た時、どう解釈し次につなげたか
- 時間的制約の中で、どのように優先順位をつけたか
具体的な質問例:
- 「探究の過程で最も苦労した点は何でしたか?」
- 「その困難をどのように乗り越えましたか?」
- 「もし同じ状況に再び直面したら、どう対処しますか?」
2. 継続性と改善のサイクルを確認する
粘り強さは、継続的な取り組みと改善から見えてきます。
評価ポイント:
- 探究活動の期間と頻度(週何時間、何ヶ月継続したか)
- 振り返りと改善のサイクルが確立されているか
- フィードバックを受けてどう行動を変えたか
- 最初と最後で何がどう変化したか
3. 内発的動機の強さを測る
外的な報酬や評価ではなく、内なる興味や使命感から行動しているかが重要です。
評価ポイント:
- 探究テーマへの個人的な思い入れ
- 授業時間外での自主的な活動
- 探究終了後も継続している活動
- 他者に語る時の熱量や具体性
「協働性」を探究活動から評価する方法
「協働性」は、多様な他者と建設的に関わり、共通の目標に向かって協力する能力です。グループ探究はもちろん、個人探究でも協働性は評価可能です。
1. 役割分担と貢献度を分析する
グループ活動において、どのような役割を担い、どう貢献したかを詳しく聞き取ります。
評価ポイント:
- 自分の強みを活かした役割を見つけられたか
- 他のメンバーの強みを引き出す工夫をしたか
- 困っているメンバーをどうサポートしたか
- 全体の進捗管理にどう関わったか
具体的な質問例:
- 「グループ内でのあなたの役割は何でしたか?」
- 「メンバー間で意見が対立した時、どう対処しましたか?」
- 「他のメンバーから学んだことは何ですか?」
2. コミュニケーション能力を観察する
協働性の基盤となるコミュニケーション能力を、具体的なエピソードから評価します。
評価ポイント:
- 自分の意見を分かりやすく伝える力
- 他者の意見を傾聴し理解する姿勢
- 建設的な議論を促進する能力
- 合意形成に向けた調整力
3. 外部との連携・協力関係を評価する
探究活動では、学校外の人々との協働も重要な評価対象です。
評価ポイント:
- 専門家へのインタビューをどう実現したか
- 地域の人々との関係をどう構築したか
- 協力を得るためのコミュニケーション方法
- 感謝の気持ちをどう表現したか
非認知能力評価の注意点と課題
非認知能力の評価には、いくつかの重要な注意点があります。
評価の客観性をどう担保するか
非認知能力は主観的な評価になりやすいという課題があります。以下の工夫が必要です。
- 複数の評価者による評価:異なる視点からの評価を総合
- 具体的な行動指標の設定:抽象的な概念を行動レベルに落とし込む
- ルーブリックの活用:評価基準を明確化し共有
- エビデンスベースの評価:具体的な成果物や記録に基づく判断
文化的背景や個人差への配慮
非認知能力の表れ方は、文化的背景や個人の特性によって異なります。
- 内向的な生徒の協働性をどう評価するか
- 失敗を語ることへの文化的な抵抗感
- 言語化が苦手な生徒への配慮
- 多様な表現方法の受け入れ
一時点での評価の限界
非認知能力は状況や時期によって変動する可能性があります。
- 探究活動全体を通じた変化を見る
- 複数の場面での行動を総合的に評価
- 成長の可能性も含めて判断
- 環境要因の影響を考慮
Study Valley TimeTactによる解決アプローチ
Study Valley TimeTactは、非認知能力の評価を支援する様々な機能を提供し、より客観的で公正な評価を可能にします。
プロセスの可視化による粘り強さの評価
TimeTactは探究活動の全プロセスを時系列で記録し、粘り強さを客観的に評価できます。
- 活動ログから見る継続性の分析
- 困難に直面した際の対処記録
- 改善サイクルの頻度と質の可視化
- 自主的な活動時間の自動集計
協働活動の詳細な記録と分析
グループ活動における個人の貢献度を明確に把握できます。
- メンバー間のコミュニケーション履歴
- 役割分担と実際の活動記録の照合
- 相互評価機能による多面的な評価
- 外部協力者とのやり取りの記録
評価の標準化とトレーニング支援
評価者間のばらつきを最小化するツールを提供します。
- 非認知能力評価のルーブリックテンプレート
- 評価者向けのトレーニングコンテンツ
- 評価結果の統計的分析機能
- 優良事例の共有プラットフォーム
長期的な成長の追跡
一時点の評価ではなく、継続的な成長を評価できます。
- 高校3年間の成長曲線の可視化
- 各時期の振り返り記録の蓄積
- メンターからのフィードバック履歴
- 自己評価と他者評価の比較分析
まとめ
非認知能力、特に「粘り強さ」と「協働性」は、大学での学びや社会での活躍に不可欠な能力です。これらは探究活動のプロセスを丁寧に観察することで、ある程度客観的に評価することが可能です。
重要なのは、一つの場面や成果物だけで判断するのではなく、探究活動全体を通じた行動パターンや成長を見ることです。困難への対処方法、継続性、他者との関わり方など、具体的な行動に注目することで、非認知能力の本質が見えてきます。
ただし、評価の客観性や公平性を保つためには、適切な評価基準の設定と評価者のトレーニングが欠かせません。Study Valley TimeTactのようなツールを活用することで、プロセスの可視化と評価の標準化が進み、より信頼性の高い非認知能力評価が実現できるでしょう。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。