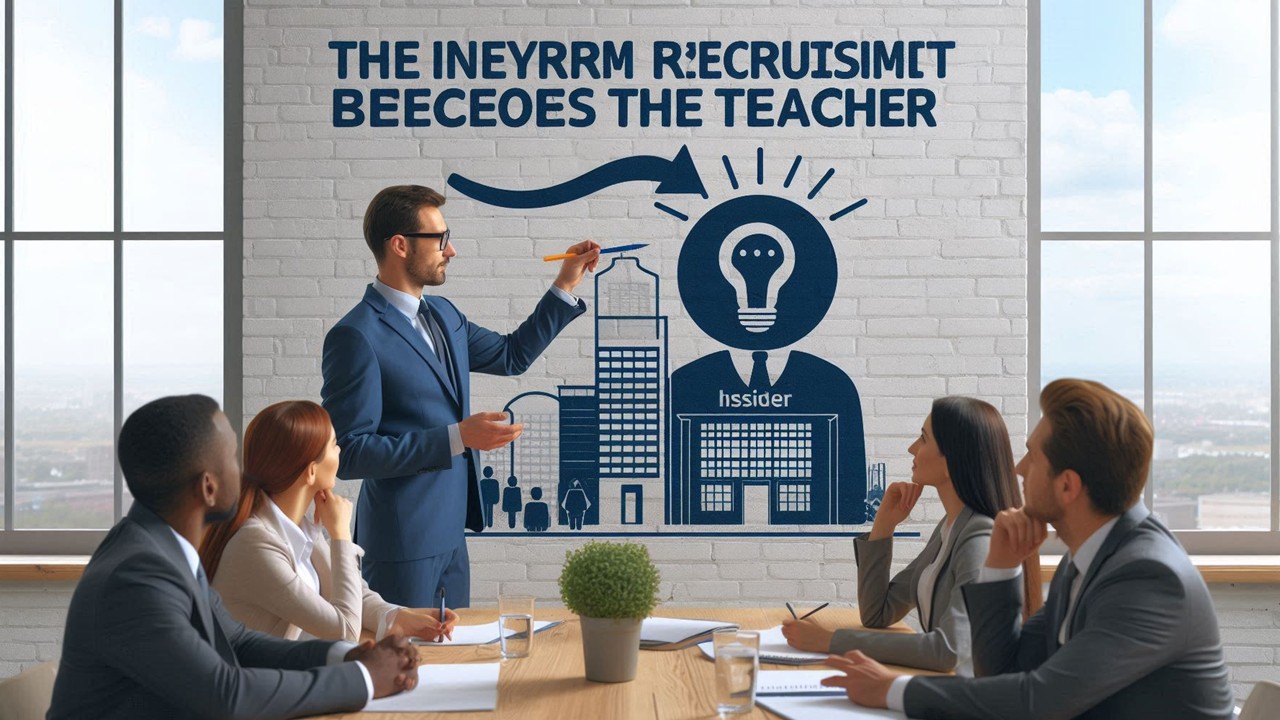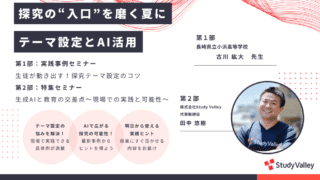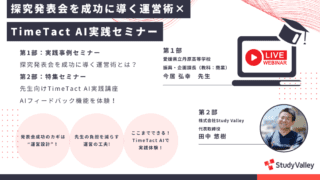企業の「中の人」が先生になる。社員の専門性を活かした、新しい採用広報の形
採用説明会で人事部の説明を聞いても、高校生にはピンとこない─そんな経験はありませんか?「弊社の理念は…」「福利厚生は充実していて…」という定型的な説明では、Z世代の心に響きません。彼らが本当に知りたいのは、実際にその企業で働く人たちのリアルな姿であり、仕事を通じて社会にどんな価値を提供しているかという具体的なストーリーです。
そこで注目されているのが、現場で活躍する社員が「先生」となって高校生に直接教える、新しい形の採用広報です。エンジニアがプログラミングを、マーケターがSNS戦略を、研究者が最先端技術を─それぞれの専門性を活かして高校の探究学習をサポートすることで、企業の魅力を肌で感じてもらう。本記事では、この「社員講師型採用広報」の具体的な実践方法と、すでに成果を上げている企業の事例を詳しく紹介します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
なぜ今、社員が「先生」になることが効果的なのか
従来の採用広報の限界と、社員講師型アプローチが注目される背景を整理しましょう。
1. Z世代が求める「リアル」と「体験」
デジタルネイティブのZ世代は、企業の公式情報よりも、実際に働く人々の生の声を重視します。
Z世代の情報収集の特徴:
- 企業の公式サイトよりもSNSでの社員の発信を信頼
- きれいにまとめられた情報より、失敗談も含むリアルなストーリーに共感
- 受動的な情報収集より、インタラクティブな体験を通じた理解を好む
- 「何をしている会社か」より「どんな人が働いているか」に関心
社員が先生となることで、これらのニーズに直接応えることができます。
2. 探究学習という新しい接点の活用
高校の探究学習は、企業にとって絶好の機会です。
探究学習の特徴が生む可能性:
- 年間50時間以上の授業時間が確保されている
- 実社会の課題を扱うため、企業の専門性が直接活きる
- 生徒は主体的に学ぶ姿勢で臨んでいる
- 成績評価に関わるため、真剣に取り組む
この枠組みを活用することで、自然な形で高校生との接点を持つことができます。
3. 専門性の価値が高まる時代
AI時代において、人間の専門性の価値はますます高まっています。
専門性が持つ採用広報上の価値:
- その道のプロから直接学べる機会は、高校生にとって貴重
- 専門知識を分かりやすく伝える姿勢が、企業文化を体現
- 最先端の技術や知識に触れることで、業界への興味を喚起
- 「こんな大人になりたい」というロールモデルの提示
4. 双方向性がもたらす深い理解
一方的な情報提供ではなく、対話を通じた相互理解が可能になります。
双方向コミュニケーションの効果:
- 高校生の質問から、彼らの関心事や価値観を直接把握
- 社員も高校生から新鮮な視点や気づきを得る
- 継続的な関係構築により、信頼関係が醸成される
- フィードバックを通じて、採用広報の改善点も見えてくる
社員講師が担える5つの役割
社員が高校の探究学習で果たせる役割は多岐にわたります。企業の特性に応じて、最適な関わり方を選択しましょう。
1. 専門知識の提供者
各分野のスペシャリストとして、高校生では調べきれない専門的な知識を提供します。
具体例:
- IT企業のエンジニア:「AIの仕組みと社会実装」についての技術解説
- 食品メーカーの研究者:「食品添加物の安全性」に関する科学的知見の提供
- 金融機関のアナリスト:「地域経済の分析手法」についての実践的指導
- 製造業の品質管理担当:「統計的品質管理」の基礎と応用
ポイント:
専門用語を使いすぎず、高校生のレベルに合わせて分かりやすく説明することが重要です。
2. メンターとしての伴走者
探究活動全体を通じて、継続的にアドバイスやフィードバックを提供します。
メンタリングの内容:
- 課題設定の妥当性についてのアドバイス
- 調査方法や分析手法の提案
- 行き詰まったときの新たな視点の提供
- プレゼンテーション資料へのフィードバック
成功のコツ:
答えを教えるのではなく、生徒自身が答えを見つけられるよう導くことが大切です。
3. プロジェクト課題の提供者
企業が実際に直面している課題を、高校生向けにアレンジして提供します。
課題例:
- 「若者向け新商品のアイデア提案」(消費財メーカー)
- 「地域の空き家活用ビジネスプラン」(不動産会社)
- 「SNSを活用した環境啓発キャンペーン」(環境関連企業)
- 「高齢者にやさしいアプリUI設計」(IT企業)
効果:
実際のビジネス課題に取り組むことで、企業の仕事内容を深く理解してもらえます。
4. キャリアモデルの提示者
自身のキャリアストーリーを通じて、多様な職業選択の可能性を示します。
伝えるべき内容:
- なぜこの仕事を選んだのか(原体験やきっかけ)
- 仕事のやりがいと難しさ(リアルな両面)
- 必要なスキルや知識(具体的な学習方法も含めて)
- 失敗経験とそこからの学び
- 将来のキャリアビジョン
注意点:
美化しすぎず、苦労や迷いも含めて正直に語ることで、共感を得られます。
5. 企業文化の体現者
社員の振る舞いや考え方を通じて、企業文化を肌で感じてもらいます。
企業文化を伝える要素:
- 問題解決へのアプローチ方法
- チームワークの重要性と実践
- 失敗を恐れない挑戦の姿勢
- 顧客や社会への価値提供の考え方
- 継続的な学習と成長への意欲
効果的な伝え方:
説教臭くならないよう、具体的なエピソードを交えながら自然に伝えることがポイントです。
社員講師プログラムの設計と実施手順
効果的な社員講師プログラムを実施するための、具体的な手順を解説します。
ステップ1:社内体制の構築(準備期間:2-3ヶ月前)
1. プロジェクトチームの結成
- 人事部門:全体統括、学校との窓口
- 広報部門:活動の記録と発信
- 各部門:講師候補者の選定と支援
- 経営層:活動の承認とバックアップ
2. 講師候補者の選定基準
- 専門性:担当分野で3年以上の実務経験
- コミュニケーション力:分かりやすく説明できる
- 教育への情熱:若者の成長を支援したい意欲
- 時間的余裕:準備と実施に必要な時間を確保できる
3. 社内の理解と協力の獲得
- 経営層への説明:採用戦略としての位置づけを明確化
- 部門長への協力要請:業務時間内の活動承認
- 同僚への周知:チーム内での業務調整への理解
ステップ2:学校との連携構築(2ヶ月前)
1. アプローチ方法
- 教育委員会を通じた正式な申し入れ
- 既存の取引先や社員の出身校から開始
- 地域の高校ネットワークの活用
- 探究学習支援プラットフォームの利用
2. 学校側のニーズ把握
- 探究学習の年間計画と重点テーマ
- 生徒の学力レベルと興味関心
- 希望する支援内容と頻度
- 施設・設備面での制約事項
3. 実施条件の調整
- 実施時期と回数(単発か継続か)
- 対象学年とクラス数
- オンライン/オフラインの選択
- 費用負担の有無(原則無償が望ましい)
ステップ3:プログラム内容の設計(1ヶ月前)
1. 学習目標の設定
- 知識面:何を理解してもらうか
- スキル面:どんな能力を身につけてもらうか
- 態度面:どんな意識変化を促すか
2. カリキュラムの構成
- 導入(15分):自己紹介、企業紹介、本日の目標
- 講義(30分):専門知識の解説、事例紹介
- ワーク(30分):グループディスカッション、簡単な実習
- 発表・まとめ(15分):成果共有、質疑応答、次回への宿題
3. 教材・資料の準備
- スライド資料(視覚的で分かりやすいデザイン)
- ワークシート(生徒が記入しやすい形式)
- 参考資料(さらに学びたい生徒向け)
- 企業紹介資料(採用情報も含む)
ステップ4:講師のトレーニング(2週間前)
1. 教育スキルの向上
- 高校生の発達段階と特性の理解
- 分かりやすい説明のテクニック
- 質問への適切な対応方法
- グループワークのファシリテーション
2. リスク管理
- 個人情報保護(生徒の情報、企業の機密情報)
- ハラスメント防止(適切な距離感の保持)
- SNS等での情報発信ルール
- 緊急時の対応方法
3. リハーサルの実施
- 社内でのプレ授業実施
- 時間配分の確認
- 想定質問への回答準備
- 改善点のフィードバック
ステップ5:実施と振り返り(当日〜1週間後)
1. 当日の運営
- 早めの到着と会場設営
- 学校側担当者との最終確認
- 生徒の反応を見ながら柔軟に対応
- 記録用の写真撮影(許可を得て)
2. フィードバックの収集
- 生徒アンケート:理解度、満足度、興味の変化
- 教員からの評価:目標達成度、改善提案
- 社員講師の自己評価:手応え、課題
3. 改善と展開
- フィードバックを基にした内容改善
- 成功事例の社内共有
- 他校への横展開の検討
- 継続的な関係構築の方策
成功事例:先進企業の取り組み
実際に社員講師型採用広報で成果を上げている企業の事例を紹介します。
事例1:IT企業A社「プログラミング・メンター制度」
概要:
エンジニア社員が高校の情報科目と連携し、探究学習でのアプリ開発をサポート。
特徴:
- 3ヶ月間の継続的なメンタリング
- オンラインとオフラインのハイブリッド実施
- 最終成果物は学校の文化祭で発表
- 優秀作品は企業のイベントでも紹介
成果:
- 参加生徒の80%が情報系学部への進学を希望
- 翌年度のインターンシップ応募者が3倍に増加
- 地域での企業認知度が大幅に向上
- 社員のモチベーション向上(教える喜びを実感)
事例2:製造業B社「ものづくり探究ラボ」
概要:
工場見学と連動し、品質管理や生産技術について実践的に学ぶプログラム。
特徴:
- 実際の製造ラインでの課題を教材化
- 統計的品質管理の基礎を高校生向けにアレンジ
- 改善提案を実際に現場で試行
- 若手社員と高校生の交流会も実施
成果:
- 地元工業高校との包括連携協定締結
- 高校生の提案から2件の業務改善を実現
- 理系女子の製造業への関心向上
- 地域での雇用ブランド力の強化
事例3:金融機関C社「地域経済探究プロジェクト」
概要:
地域経済の課題を高校生と一緒に分析し、活性化策を提案するプログラム。
特徴:
- 実際の経済データを使った分析指導
- 地元企業へのインタビュー調査をサポート
- ビジネスプランコンテストへの出場支援
- 優秀提案は実際の融資案件として検討
成果:
- 参加高校が5校から15校に拡大
- 地域メディアでの露出増加
- 高校生の提案から新規事業が誕生
- 若手行員の企画力・指導力が向上
効果測定と継続的改善のポイント
社員講師プログラムの効果を最大化するには、適切な効果測定と改善が不可欠です。
1. 定量的指標の設定
短期的指標(〜1年):
- プログラム参加生徒数
- 生徒の満足度スコア(5段階評価の平均)
- 企業認知度の変化(事前事後アンケート)
- 企業への興味関心度の変化
- SNSでの言及数やエンゲージメント率
中期的指標(1-3年):
- インターンシップへの応募数
- 採用説明会への参加率
- 出身高校別の応募者数推移
- 採用選考での言及率(志望動機での言及)
長期的指標(3年〜):
- 実際の採用実績(参加者からの入社数)
- 入社後の定着率とパフォーマンス
- 企業ブランド調査での評価向上
- 地域での採用競争力の変化
2. 定性的評価の重要性
収集すべき定性データ:
- 生徒の感想文やレポート内容の分析
- 教員からの詳細なフィードバック
- 社員講師の気づきや学び
- 保護者からの反応(学校経由で収集)
分析の観点:
- 企業イメージの変化(具体的な言葉の変化)
- 職業観・キャリア観への影響
- 学習意欲の向上度合い
- 社員と生徒の相互理解の深まり
3. PDCAサイクルの確立
Plan(計画):
- 前回の振り返りを踏まえた改善計画
- 新しい学校・テーマへの展開計画
- 講師陣の拡充・育成計画
Do(実施):
- 計画に基づいた着実な実行
- 現場での柔軟な対応
- 記録の徹底(写真、動画、メモ)
Check(評価):
- データに基づく客観的評価
- 関係者全員からのフィードバック収集
- 成功要因と課題の明確化
Action(改善):
- 課題解決のための具体的アクション
- 成功事例の横展開
- プログラムの進化・拡大
社員講師を成功させる10の秘訣
多くの企業の実践から見えてきた、成功のための重要ポイントをまとめます。
1. トップのコミットメントを得る
経営層が価値を理解し、積極的に支援する体制を作ることが大前提です。社員が安心して時間を使えるよう、業務として正式に認定することが重要です。
2. 講師の自主性を尊重する
強制ではなく、自ら手を挙げた社員を講師にすることで、情熱を持った指導が可能になります。
3. 準備時間を十分に確保する
質の高いプログラムには相応の準備が必要です。本番の3倍以上の準備時間を見込みましょう。
4. 高校生の視点に立つ
企業の都合ではなく、高校生にとって価値ある内容になっているか常に確認することが大切です。
5. 失敗を恐れない文化を作る
最初から完璧を求めず、試行錯誤しながら改善していく姿勢が重要です。
6. 社内での情報共有を活発に
講師経験者の知見を共有し、組織として学習していく仕組みを作りましょう。
7. 学校との信頼関係を大切に
単発の関係ではなく、継続的なパートナーシップを構築することで、効果が高まります。
8. 適切な記録と発信
活動の様子を記録し、社内外に発信することで、取り組みの価値を可視化できます。
9. 講師自身の成長機会と捉える
教えることで学ぶ機会として、社員育成の観点からも価値づけしましょう。
10. 長期的視点を持つ
すぐに採用につながらなくても、地域での信頼構築や企業ブランディングとして価値があることを理解しましょう。
Study Valley TimeTactで社員講師プログラムを加速させる
社員講師プログラムの企画・実施・評価には、多大な労力と専門知識が必要です。Study Valley TimeTactは、企業と高校をつなぎ、効果的な社員講師プログラムの実現をトータルサポートします。
TimeTactが提供する価値:
1. 学校とのマッチング支援
全国の高校の探究学習ニーズをデータベース化。企業の専門性や地域性に合った最適な高校をマッチングします。煩雑な調整業務から解放され、プログラム内容の充実に注力できます。
2. カリキュラム設計支援
教育の専門家が、企業の専門性を高校生向けにカスタマイズ。学習指導要領に準拠しつつ、企業の魅力を最大限に伝えるプログラムを設計します。
3. 講師トレーニングプログラム
高校生への指導経験がない社員でも安心。効果的な教え方、ファシリテーション技術、リスク管理まで、包括的な研修を提供します。
4. 実施運営サポート
オンライン授業のテクニカルサポートから、当日の運営補助まで。企業の負担を最小限に抑えながら、質の高いプログラムを実現します。
5. 効果測定・分析レポート
参加生徒の学習成果、意識変化、企業への関心度などを詳細に分析。採用戦略へのインサイトを提供し、プログラムの継続的改善を支援します。
さらに、TimeTactのプラットフォーム上では、他企業の成功事例や教材を参考にできるため、ゼロから作る必要がありません。すでに500社以上の企業が活用し、高い成果を上げています。
まとめ:社員一人ひとりが企業の顔となる時代へ
「企業の中の人が先生になる」─この新しい採用広報の形は、単なる人材獲得の手段を超えた価値を持っています。それは、企業と若者が本音で向き合い、相互理解を深める貴重な機会であり、社員自身の成長の場でもあり、地域社会への貢献でもあります。
Z世代は、企業の看板や待遇だけでなく、そこで働く人々の姿勢や価値観を重視します。社員一人ひとりが企業の顔となり、その専門性と人間性を通じて企業の魅力を伝える─これこそが、これからの採用広報の本質なのです。
高校の探究学習という新しいフィールドで、あなたの企業の社員は、どんな「先生」になれるでしょうか。その一歩を踏み出すことが、未来の優秀な人材との出会いにつながることでしょう。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。