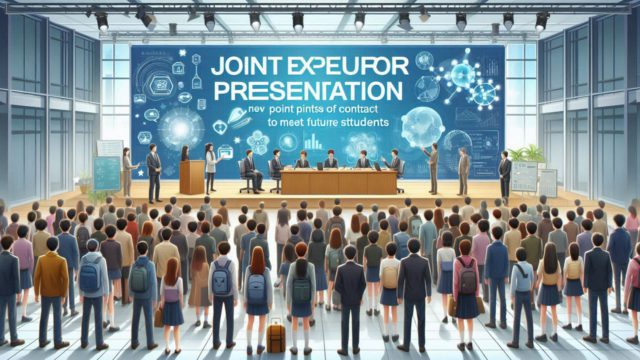「高大連携」が大学のブランディングに繋がる。高校・地域社会から選ばれる大学になるために
少子化が加速し、18歳人口が減少し続ける中、多くの大学が学生募集に苦戦を強いています。従来の偏差値や知名度だけに頼った学生募集では限界が見え始め、大学は新たな価値創造と差別化戦略を模索しています。その中で注目されているのが「高大連携」です。単なる出張講義や大学見学にとどまらない、探究学習を軸とした継続的な高大連携こそが、大学のブランディングを根本から変える可能性を秘めています。本記事では、なぜ高大連携が大学ブランディングに直結するのか、そして地域社会から選ばれる大学になるための具体的な方策について詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
少子化時代に大学が直面する3つの危機と、従来型募集活動の限界
現在、日本の大学は前例のない厳しい環境に置かれています。文部科学省の統計によると、18歳人口は1990年代のピーク時から比べて約40%減少し、2040年には現在よりもさらに約20%減少することが予測されています。この急激な人口減少は、大学経営に以下の3つの深刻な危機をもたらしています。
1. 学生獲得競争の激化と定員割れのリスク
日本私立学校振興・共済事業団の調査によると、2023年度には私立大学の約53%が定員割れを起こしており、この傾向は今後さらに加速すると予測されています。特に地方の中小規模大学では、学生確保が経営存続に直結する深刻な問題となっています。従来のような「待ちの姿勢」では、もはや学生を集めることは困難です。
2. 高校生の大学選択基準の変化
Z世代と呼ばれる現在の高校生は、単に偏差値や知名度だけで大学を選ぶ時代ではなくなりました。彼らは「その大学で何が学べるのか」「社会課題の解決にどう貢献できるのか」「自分の探究テーマをどう深められるのか」という視点で大学を選ぶようになっています。2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」により、高校生は自ら課題を設定し、解決策を探る経験を積んでいます。この経験が、大学選びの基準を根本的に変えているのです。
3. 地域社会との関係性の希薄化
大学は本来、地域の知の拠点として機能すべき存在です。しかし、多くの大学が「象牙の塔」と揶揄されるように、地域社会との接点が限定的になっています。地域の高校や企業、自治体との連携が不十分なため、大学の持つ知的資源が地域に還元されず、結果として地域からの支持や信頼を得られていない状況があります。
なぜ「高大連携」が大学ブランディングの切り札となるのか
このような危機的状況を打開する鍵となるのが、戦略的な高大連携の推進です。高大連携とは、高校と大学が連携して教育を行うことを指しますが、その効果は単なる教育連携にとどまりません。実は、効果的な高大連携は大学のブランディングを根本から変革する力を持っています。
高大連携がもたらす5つのブランディング効果
1. 早期からの大学認知度向上
高校1年生、2年生の段階から継続的に接点を持つことで、大学の魅力や特色を早期から浸透させることができます。順天堂大学の事例では、「高大連携を重視する開かれた学部」として、多様な教員の専門的知見を活用した模擬授業を実施。これにより、高校生の間での認知度が大幅に向上し、志願者数の増加につながっています。
2. ミスマッチの解消と質の高い学生の獲得
探究学習を通じた高大連携により、高校生は大学での学びを具体的にイメージできるようになります。これにより、入学後のミスマッチを防ぎ、明確な目的意識を持った学生を獲得できます。関西学院大学では「探究評価型入学試験」を導入し、高校での探究活動を評価することで、主体的に学ぶ意欲の高い学生の獲得に成功しています。
3. 地域社会からの信頼獲得
宮城大学の事例では、2019年に「高大連携推進室」を設置し、様々な部署で実施されていた高大連携の取り組みを一本化。これにより、継続的なプログラムの実施が可能となり、地域の高校からの信頼を獲得しています。大学が地域の教育に貢献する姿勢を示すことで、地域社会全体からの支持を得ることができるのです。
4. 大学の研究・教育内容の可視化
高大連携を通じて、大学の研究内容や教育の特色を高校生に直接伝えることができます。岡山理科大学では、医療技術職に関する講義や理系学習に必要な英語力に関する講義など、具体的な専門分野の魅力を伝える出張講義を実施。これにより、大学の強みが明確に伝わり、志願者の質の向上につながっています。
5. 持続可能な関係性の構築
単発的なイベントではなく、継続的な高大連携プログラムを実施することで、高校との長期的な信頼関係を構築できます。京都府立北稜高校と京都光華女子大学の連携事例では、カリキュラム設計から参加し、連続的に講座を持つことで、深い関係性を築いています。
探究学習を核とした高大連携の実践方法
では、具体的にどのような高大連携を実施すれば、大学ブランディングにつながるのでしょうか。ポイントは、高校で必修化された「探究学習」を軸とした連携プログラムの構築です。
1. 大学の専門性を活かした探究テーマの提供
大学の各学部・学科が持つ専門性を活かし、高校生が取り組める探究テーマを提供することが重要です。例えば、環境学部であれば地域の環境問題、経済学部であれば地域経済の活性化など、地域に根ざした課題を探究テーマとして設定します。奈良女子大学の「探究力入試Q」では、「自分で問いを立ててそれを解き明かしていく」ことを重視し、大学での学びにつながる探究活動を評価しています。
2. 継続的な伴走支援の実施
単発の出張講義ではなく、高校生の探究活動に対して継続的な支援を行うことが効果的です。大学教員や大学生が定期的に高校を訪問し、探究活動へのアドバイスを行ったり、大学の施設を活用した実験・調査の機会を提供したりします。大阪大学では「高大接続サポーター」として256名の学生が登録し、高校生の探究学習をサポートしています。
3. 高校教員との協働体制の構築
高大連携を成功させるためには、高校教員との密な連携が不可欠です。定期的な情報交換会の開催、探究学習の評価基準の共有、指導方法に関する研修会の実施など、高校教員をサポートする体制を整えることが重要です。
4. 地域課題解決型プロジェクトの実施
大学、高校、地域が一体となって地域課題の解決に取り組むプロジェクトを実施することで、実践的な学びの場を提供できます。総務省の「域学連携」事業では、大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域住民やNPO等と共に課題解決に取り組む活動を支援しています。このような取り組みは、大学の社会貢献度を高め、地域からの評価向上につながります。
5. 探究成果発表会の共同開催
高校生の探究成果を大学で発表する機会を設けることで、高校生に大学の雰囲気を体験してもらうとともに、大学教員から専門的なフィードバックを受ける機会を提供できます。これにより、高校生の学習意欲が高まり、大学への進学意欲も向上します。
Study Valley TimeTactが実現する、新しい高大連携の形
このような高大連携を効果的に実施するためには、適切なプラットフォームとサポート体制が必要です。そこで注目されているのが、Study Valleyが提供する探究学習支援プラットフォーム「TimeTact」です。
TimeTactが高大連携にもたらす5つの革新
1. 大学の研究・特色を探究テーマ化
TimeTactでは、大学の研究内容や特色を基にした探究テーマを掲載し、全国の高校生と大学との連携をサポートしています。これにより、大学は自身の強みを活かした探究テーマを提供でき、高校生は興味のある分野の大学と直接つながることができます。
2. デジタルプラットフォームによる距離の壁の解消
オンラインプラットフォームを活用することで、地理的な制約を超えて全国の高校と連携することが可能になります。これまで訪問が困難だった遠隔地の高校とも、継続的な関係を構築できます。また、デジタル化により、学校訪問や対面説明会に比べてコストを抑えながら、重要なターゲット層にアプローチできます。
3. 探究活動の進捗管理と評価の可視化
TimeTactは、高校生の探究活動の進捗を可視化し、大学側が適切なタイミングでサポートできる仕組みを提供しています。400校以上の導入実績を持ち、探究学習に特化したプラットフォームとして、効果的な指導を可能にします。
4. 継続的な関係構築を支援する面談機能
単発的な募集活動とは異なり、探究コンテンツの提供とそれに関するアドバイス・質疑応答を通じて、継続的に高校生と関係性を築くことができます。面談機能により、探究活動を通じた進路指導も可能となり、高校生の進学意欲向上につながります。
5. 生成AIを活用した探究支援
2024年に発表されたTimeTactの新機能では、生成AIを活用した探究学習支援により、教員の業務負荷を95%軽減することが可能になりました。これにより、大学側も効率的に多くの高校生をサポートでき、より質の高い高大連携を実現できます。
まとめ:高大連携で実現する、選ばれる大学への変革
少子化時代において、大学が生き残るためには、従来の募集活動から脱却し、高校や地域社会との深い関係性を構築することが不可欠です。探究学習を軸とした高大連携は、単なる学生募集の手段ではなく、大学のブランド価値を根本から高める戦略的な取り組みです。
高大連携を通じて、大学は以下の価値を創造できます:
- 早期からの認知度向上と信頼関係の構築
- ミスマッチの解消による質の高い学生の獲得
- 地域社会への貢献による評価の向上
- 大学の研究・教育内容の効果的な発信
- 持続可能な募集活動の実現
高大連携は、大学が「選ぶ側」から「選ばれる側」へと変わった時代において、最も効果的なブランディング戦略の一つです。Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、効率的かつ効果的な高大連携を実現し、地域社会から愛され、高校生から選ばれる大学へと変革することができるでしょう。今こそ、高大連携を通じた新たな大学ブランディングに取り組む時です。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。