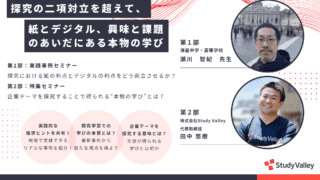早期接触が定員充足のカギ。高校1、2年生に大学の魅力を効果的に届けるアプローチ
大学入試制度の多様化と18歳人口の減少により、従来の高校3年生中心の学生募集戦略では限界が見えています。成功している大学に共通するのは、高校1、2年生への早期アプローチを戦略的に実施していることです。早い段階から大学の魅力を伝え、志望校として意識してもらうための効果的な手法を解説します。
多くの大学では、いまだに高校3年生の春からの募集活動に重点を置いています。しかし、総合型選抜の拡大により、生徒の進路選択は高校2年生の段階で実質的に始まっています。さらに、探究学習の必修化により、高校1年生から自分の興味・関心を深め、将来の進路を意識する機会が増えました。この変化に対応できている大学とそうでない大学で、定員充足率に大きな差が生まれているのが現実です。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
なぜ今、高校1、2年生へのアプローチが重要なのか
高校生の進路選択行動が大きく変化している今、早期接触の重要性はかつてないほど高まっています。その背景には、教育環境と入試制度の構造的な変化があります。
探究学習がもたらした進路選択の早期化
2022年度から必修化された「総合的な探究の時間」により、高校生は1年次から自分の興味・関心を深く掘り下げる機会を得ています。
- 高校1年生:探究テーマの設定を通じて、自分の興味分野を明確化
- 高校2年生:探究活動の深化により、学びたい学問領域を具体化
- 高校3年生:探究の成果を活かした進路選択と入試準備
この流れにより、従来は高校3年生で行われていた「学部・学科選び」が、実質的に高校2年生の段階で始まっているのです。
総合型選抜の拡大による準備期間の長期化
総合型選抜(旧AO入試)の募集人員は年々拡大し、私立大学では全体の約15%、国公立大学でも約5%に達しています。
- 活動実績の蓄積:1年生から計画的な活動が必要
- ポートフォリオ作成:2年生から記録を開始する生徒が増加
- 志望理由の醸成:大学研究に1年以上かける生徒が主流に
情報収集行動の変化
デジタルネイティブ世代の高校生は、進路情報の収集方法も大きく変化しています。
- SNSでの情報収集:InstagramやTikTokで大学の雰囲気を確認
- オンラインイベント参加:気軽に複数大学の情報を比較
- 先輩の体験談重視:リアルな声を求める傾向が強化
これらの行動は高校1年生から始まっており、3年生になる頃には既に志望校がほぼ固まっているケースが増えています。
高校1、2年生が大学に求める情報とは
効果的なアプローチを行うためには、高校1、2年生がどのような情報を求めているかを正確に理解する必要があります。彼らのニーズは、3年生とは大きく異なります。
1. 学問分野の具体的なイメージ
高校1、2年生の多くは、大学で学ぶ内容について漠然としたイメージしか持っていません。
- 「○○学部では何を学ぶのか」の具体的な説明
- 高校の教科との違いや発展性の明示
- 卒業後のキャリアパスの多様性提示
- 研究の面白さを伝える体験型コンテンツ
2. 大学生活のリアルな姿
入試情報よりも、大学生活そのものへの関心が高い時期です。
- キャンパスライフ:授業、サークル、アルバイトのバランス
- 学生の成長ストーリー:入学時と現在の変化
- 施設・設備:学習環境や生活環境の充実度
- 大学の雰囲気:学生や教員の人柄、校風
3. 探究活動との接続性
探究学習に取り組む中で、大学での学びとの関連性を意識し始めます。
- 探究テーマを深められる研究室の存在
- 高校の探究を評価する入試制度の有無
- 大学での探究的な学びの具体例
- 高大連携プログラムへの参加機会
効果的な早期アプローチの具体的手法
高校1、2年生に大学の魅力を効果的に伝えるには、従来の広報手法の見直しが必要です。成功事例から見えてきた、効果的なアプローチ方法を紹介します。
1. 探究学習支援を通じた接点づくり
探究学習のサポートは、自然な形で高校生と接触できる最良の機会です。
- 探究メンター派遣
- 大学院生や学部生を高校に派遣
- 探究活動のアドバイザーとして定期的に関与
- 年間を通じた継続的な関係構築
- オンライン探究相談会
- 月1回程度の定期開催
- テーマ別の専門教員による助言
- 参加者データベースの構築と継続フォロー
- 探究成果発表会の共催
- 大学施設を会場として提供
- 教員による講評・フィードバック
- 優秀者への研究室訪問機会の提供
2. 体験型プログラムの充実
座学中心ではなく、実際に「大学の学び」を体験できるプログラムが効果的です。
- 1日研究室体験
- 少人数制で研究活動を体験
- 大学院生との交流時間を確保
- 実験や調査の一部を実際に経験
- 高校生向けゼミナール
- 月1回、半年間の継続プログラム
- 大学の授業形式を体験
- 修了証の発行でモチベーション維持
- サマーキャンプ・スプリングキャンプ
- 2泊3日程度の集中プログラム
- 他校の生徒との交流機会
- 大学生活の疑似体験
3. デジタルコンテンツの戦略的活用
高校1、2年生の情報収集行動に合わせた、デジタル戦略が不可欠です。
- SNSでの日常的な情報発信
- Instagram:キャンパスライフの日常を切り取る
- TikTok:研究の面白さを短時間で伝える
- YouTube:在学生インタビューや模擬授業
- バーチャルキャンパスツアー
- 360度カメラでの施設紹介
- 在学生ガイドによるライブ配信
- チャット機能での質問対応
- オンライン個別相談の常設
- 予約不要の相談窓口設置
- LINEやZoomでの気軽な相談
- AIチャットボットでの24時間対応
早期アプローチを成功させる組織体制と評価方法
効果的な早期アプローチを実現するには、組織全体での取り組みと、適切な効果測定が必要です。
推進体制の構築
- 専門チームの設置
- 高校1、2年生対応の専任スタッフ配置
- 入試広報部門と教学部門の連携強化
- 学生スタッフの積極的活用
- 高校との関係構築
- 進路指導部だけでなく、探究担当教員との連携
- 定期的な情報交換会の開催
- 高校のニーズに応じたプログラム開発
- 継続的なフォローアップ体制
- CRMシステムでの接触履歴管理
- 学年進行に応じた情報提供
- 個別最適化されたコミュニケーション
効果測定と改善サイクル
早期アプローチの効果を正確に測定し、PDCAサイクルを回すことが重要です。
- 定量的指標
- プログラム参加者数の推移
- 参加者の出願率・入学率
- 接触時期と志望度の相関分析
- 定性的評価
- 参加者アンケートでの満足度
- 高校教員からのフィードバック
- 入学者インタビューでの志望動機分析
- 長期的な追跡調査
- 早期接触者の入学後の成績・活躍度
- 大学へのエンゲージメント
- 卒業後の進路との相関
Study Valley TimeTactで実現する、高校との継続的な関係構築
高校1、2年生への早期アプローチで最も重要なのは、一過性の接触で終わらせない継続的な関係構築です。Study Valley TimeTactは、探究学習を軸とした高大連携を支援し、自然な形での早期接触を可能にします。
TimeTactを活用した早期アプローチの利点
- 探究活動の可視化による適切なマッチング
- 生徒の探究テーマ・関心分野をデータベース化
- 大学の研究分野とのマッチング機能
- 興味関心に基づいた的確な情報提供
- 継続的な関わりを実現する仕組み
- 探究メンターとしての大学教員・学生の登録
- オンラインでの定期的なフィードバック
- 年間を通じた成長の見守り
- 高校教員との協働を促進
- 探究指導の負担軽減による信頼関係構築
- 評価基準の共有による入試接続の明確化
- 高校のニーズを把握できるコミュニケーション機能
データに基づく戦略的アプローチ
TimeTactに蓄積されるデータを活用することで、より効果的な早期アプローチが可能になります。
- 探究テーマ分析:トレンドを把握し、需要の高い分野の講座を企画
- 活動履歴の追跡:関心の変化を把握し、適切なタイミングでアプローチ
- 成果の可視化:探究活動での成長を評価し、大学での学びにつなげる
すでに導入している大学では、TimeTactを通じた早期接触者の出願率が通常の3倍以上という成果も報告されています。
まとめ:早期アプローチは「投資」であり「関係構築」である
高校1、2年生への早期アプローチは、単なる学生募集の前倒しではありません。探究学習を通じて自己理解を深めている生徒たちに、適切なタイミングで大学の魅力を伝え、共に成長していく関係を構築することが本質です。
成功のポイントは、高校生のニーズを正確に把握し、探究学習支援や体験型プログラムを通じて継続的な接点を持つことです。デジタルツールを活用した日常的な情報発信と、対面での深い体験を組み合わせることで、効果的なアプローチが実現します。
18歳人口の減少が続く中、従来の募集戦略では限界があります。高校1、2年生の段階から計画的にアプローチし、信頼関係を構築することが、安定的な定員充足への確実な道筋となるでしょう。今こそ、早期アプローチ戦略の見直しと強化に着手すべき時です。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。