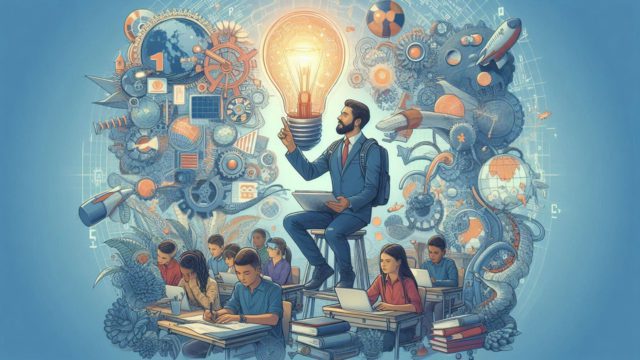高校生ならではの視点が、新たな事業アイデアのヒントに。探究連携が生むイノベーション
「既存の枠組みにとらわれない発想」「デジタルネイティブならではの着眼点」「社会課題への純粋な問題意識」。高校生との探究連携を通じて、多くの企業が想定外のイノベーションのヒントを得ています。単なるCSR活動を超えた、企業成長に直結する高校生との協働の可能性を、具体的事例とともに解説します。
企業内でのアイデア創出が行き詰まりを見せる中、外部の新鮮な視点を取り入れる「オープンイノベーション」の重要性が高まっています。その中でも注目されているのが、高校生との探究連携です。Z世代の高校生は、大人が見過ごしがちな課題を発見し、テクノロジーを自在に操り、固定観念にとらわれない解決策を提案します。本記事では、実際に高校生との協働から新事業のヒントを得た企業の事例を紹介しながら、その可能性と実践方法をお伝えします。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
なぜ高校生の視点が、企業のイノベーションにつながるのか
高校生との探究連携が企業にもたらす価値は、「異質性」と「先進性」の両面にあります。彼らの持つ独特な視点が、企業の盲点を突き、新たな可能性を開くのです。
1. デジタルネイティブとしての先進的な発想
生まれた時からインターネットに囲まれて育ったZ世代の高校生は、デジタル技術を「特別なもの」ではなく「当たり前の道具」として捉えています。
- SNSを前提とした情報流通の設計:「拡散されること」を前提としたサービス設計
- アプリファーストの思考:PCではなくスマホを起点とした発想
- AI活用への抵抗感の低さ:ChatGPTなどを日常的に使いこなす
- 仮想空間での活動が自然:メタバースやVRへの親和性の高さ
2. 既存の業界常識にとらわれない自由な発想
業界経験がないことが、むしろ強みになるケースが多くあります。
- 「できない理由」を知らない強さ:技術的制約や業界慣習を知らないからこその大胆な提案
- ユーザー視点の純粋さ:提供者側の論理に染まっていない消費者目線
- 異業種の成功事例の転用:業界の垣根を越えた発想の組み合わせ
- 「なぜ?」から始まる根本的な問い:当たり前を疑う姿勢
3. 社会課題への高い感度と行動力
SDGsネイティブとも言える彼らは、社会課題解決への意識が非常に高いです。
- 環境問題への切実な当事者意識:自分たちの将来に直結する問題として捉える
- 多様性への自然な受容:ジェンダーや国籍の違いを当然のものとして受け入れる
- 社会貢献と収益の両立志向:「儲かればいい」ではなく「意味のあるビジネス」を求める
- グローバルな視点:世界の同世代とSNSでつながる日常
実際に生まれたイノベーション事例
高校生との探究連携から、実際にどのようなイノベーションが生まれているのか。具体的な成功事例を業界別に紹介します。
【食品業界】高校生の「食の未来」探究から生まれた新商品
ある大手食品メーカーは、高校生と「2050年の食卓」をテーマに探究プロジェクトを実施しました。
- 高校生の発見:
- 昆虫食への抵抗感が同世代では予想以上に低い
- 「映える」要素があれば、新しい食材も受け入れられる
- 環境負荷の数値を可視化すると購買意欲が上がる
- 企業の気づき:
- 若年層向けマーケティングの方向性を見直し
- サステナブル商品の訴求方法を転換
- パッケージデザインに環境スコアを表示
- 成果:高校生のアイデアを活かした代替タンパク商品が、若年層を中心にヒット
【IT業界】高校生が発見した「学習アプリの盲点」
EdTech企業が高校生と共同で、既存の学習アプリの改善点を探究しました。
- 高校生の指摘:
- 「勉強している感」が強すぎて継続できない
- 友達と競争できる要素が欲しい
- TikTokのような短時間コンテンツ形式が集中しやすい
- 開発された新機能:
- 15秒で1問解けるマイクロラーニング機能
- フレンドとのリアルタイム対戦モード
- 学習時間をNFTとして記録する仕組み
- 結果:アプリの継続率が従来比3倍に向上、新規ユーザー獲得も加速
【小売業界】高校生の買い物行動分析から見えた新たな店舗形態
大手小売チェーンが、高校生の買い物行動を探究テーマに設定し、共同研究を実施しました。
- 高校生の行動パターン:
- 商品検索はInstagramから始まる
- 店舗は「体験」と「撮影スポット」として利用
- 決済は完全キャッシュレス、現金は持ち歩かない
- 新店舗コンセプト:
- インスタ映えを意識した商品ディスプレイ
- 試着室を「撮影スタジオ」として設計
- QRコード決済のみの無人レジ
- 効果:Z世代向け新業態店舗の売上が想定の2倍を記録
【製造業】高校生の「未来の移動」探究が示した新モビリティ
自動車部品メーカーが、高校生と「2030年の通学風景」を探究しました。
- 高校生の提案:
- 自動運転より「移動中に何ができるか」が重要
- 個人所有より必要な時だけ使えるシェアリング
- 移動手段自体がSNSのようなコミュニケーションツールに
- 企業の新規事業:
- 移動型学習スペースとしてのモビリティ開発
- 高校生向けマイクロモビリティのシェアサービス
- 移動データを活用した新しいSNSプラットフォーム
- 展開:実証実験を経て、新規事業として本格展開へ
高校生との探究連携を成功させる5つのポイント
単に高校生の意見を聞くだけでは、イノベーションは生まれません。効果的な協働のための実践的なポイントを紹介します。
1. 対等なパートナーとして接する
「教える・教わる」の関係ではなく、共に課題解決に取り組む姿勢が重要です。
- 高校生を「未来の顧客」として尊重
- アイデアへの真摯なフィードバック
- 実現可能性を一緒に検討する姿勢
- 失敗を恐れない実験的な雰囲気づくり
2. 企業の「リアル」を包み隠さず共有
きれいごとだけでなく、ビジネスの現実も伝えることで、より実践的なアイデアが生まれます。
- コスト意識の共有:収益性の重要性を理解してもらう
- 技術的制約の説明:現在の技術でできること・できないこと
- 市場競争の実態:競合他社の存在と差別化の必要性
- 失敗事例の開示:過去の失敗から学ぶ姿勢
3. 長期的な関係構築を前提とする
単発のイベントではなく、継続的な関わりがイノベーションを生みます。
- 年間を通じたプロジェクト設計
- 段階的な関与度の深化
- 卒業後も続く関係性の構築
- 成果の共有と次への発展
4. 社内の巻き込みと体制整備
人事部門だけでなく、事業部門も巻き込んだ全社的な取り組みが必要です。
- 経営層の理解とコミットメント
- 若手社員をメンターとして配置
- アイデアを事業化する仕組みの構築
- 成果を社内に共有する場の設定
5. 適切な評価とインセンティブ設計
高校生のモチベーションを維持し、質の高いアウトプットを得るための工夫が必要です。
- アイデアの採用可能性を明示
- 優秀提案への表彰制度
- 実現した場合のクレジット明記
- 進路に役立つ修了証の発行
イノベーション創出のための具体的な進め方
高校生との探究連携を通じてイノベーションを生み出すための、実践的なプロセスをステップごとに解説します。
Phase 1:課題設定とチーム編成(1-2ヶ月)
- 自社の課題の棚卸し
- 新規事業のアイデア不足
- 若年層向けマーケティングの行き詰まり
- 既存商品・サービスの改善点
- 高校生が取り組みやすいテーマへの翻訳
- 専門用語を使わない課題設定
- 身近な事例との関連付け
- 社会的意義の明確化
- 協力校との調整
- 学校の年間計画との整合
- 評価方法の事前合意
- 知的財産権の取り扱い確認
Phase 2:アイデア創出とプロトタイピング(3-4ヶ月)
- キックオフワークショップ
- 企業理念と事業内容の共有
- 課題の背景説明
- ゴールイメージの共有
- 定期的なメンタリング
- 週1回のオンラインミーティング
- 月1回の対面セッション
- 随時のチャット相談
- プロトタイプ作成支援
- 必要な技術・ツールの提供
- 専門家によるアドバイス
- 試作品製作の支援
Phase 3:検証と事業化検討(2-3ヶ月)
- 社内プレゼンテーション
- 経営層への直接提案機会
- 関連部署からのフィードバック
- 実現可能性の検証
- 市場調査の実施
- ターゲット層へのヒアリング
- 競合分析
- 収益性の試算
- パイロットプロジェクト
- 小規模での実証実験
- 高校生による効果測定
- 改善点の洗い出し
Study Valley TimeTactで実現する、効果的な探究連携
高校生との探究連携を成功させるには、プロジェクトの進捗管理と成果の可視化が不可欠です。Study Valley TimeTactは、企業と高校の協働プロジェクトを円滑に進めるための機能を提供します。
企業にとってのメリット
- プロジェクト進捗の可視化
- 高校生の活動状況をリアルタイムで把握
- マイルストーンごとの達成度を確認
- 早期の軌道修正が可能
- アイデアの体系的な蓄積
- すべての提案を一元管理
- カテゴリー別の整理・検索
- 過去のアイデアの再活用
- 効率的なコミュニケーション
- メンターと生徒の円滑な情報共有
- フィードバックの記録と追跡
- オンライン・オフラインの活動を統合管理
イノベーション創出を加速する機能
- アイデアコンテスト機能:優秀提案の選定と表彰をシステム化
- プロトタイプ共有機能:画像や動画での成果物共有
- 投票・評価機能:社員による人気投票でアイデアを選別
- 知財管理機能:アイデアの帰属を明確に記録
すでに導入企業では、「高校生のアイデアから3つの新規事業が生まれた」「若手社員のモチベーション向上にもつながった」といった成果が報告されています。
まとめ:高校生との協働が開く、イノベーションの新地平
高校生との探究連携は、単なる社会貢献活動ではありません。彼らの持つ「デジタルネイティブの感性」「既成概念にとらわれない発想」「社会課題への高い意識」は、企業に新たなイノベーションの種をもたらします。
重要なのは、高校生を「教育の対象」ではなく「イノベーションのパートナー」として捉えることです。対等な立場で課題に向き合い、お互いの強みを活かし合うことで、想像を超えた成果が生まれます。実際に、多くの企業が高校生との協働から新商品のアイデアを得たり、新規事業の方向性を見出したりしています。
人口減少と市場の成熟化が進む中、企業が持続的に成長するためには、従来とは異なる発想でイノベーションを起こす必要があります。高校生との探究連携は、その突破口となる可能性を秘めています。まずは小さなプロジェクトから始めて、若い世代の柔軟な発想に触れてみてはいかがでしょうか。きっと、自社の未来を変えるヒントが見つかるはずです。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。