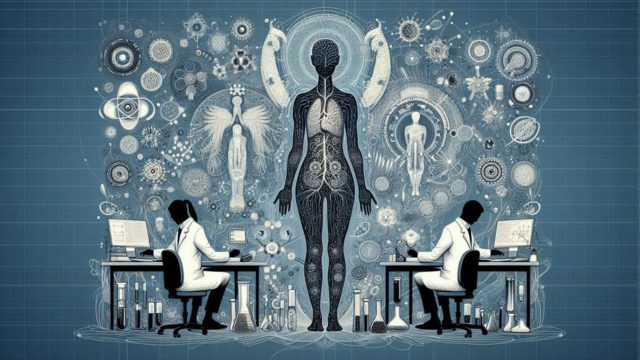高校生の探究、その「リアル」なレベル感とは?過度な期待と現実のギャップを埋める
2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」。大学入試改革と相まって、探究力を持つ学生を求める動きが加速しています。しかし、実際の高校生の探究活動のレベルは、大学側が期待するほど高いのでしょうか?総合型選抜の拡大とともに、高大接続における「探究」への期待が高まる中、現実とのギャップに悩む大学関係者も少なくありません。本記事では、高校の探究学習の実態を客観的に分析し、大学が持つべき適切な期待値と、効果的な評価・支援のあり方について考察します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
高校の探究学習、理想と現実の大きな隔たり
文部科学省は探究学習を「問題解決的な学習が発展的に繰り返されていく過程」と定義し、生徒が主体的に課題を設定し、情報収集・整理・分析を通じて解決策を導き出す能力の育成を目指しています。しかし、現場の実態はどうでしょうか。
NPO法人カタリバが2024年に実施した調査によると、高校教員の実に9割以上が探究学習に何らかの課題を感じていることが明らかになりました。具体的には「授業案やカリキュラムの設計」(49.4%)、「調べ学習で終わってしまう」(49.1%)、「校内で探究学習への理解が広がらない」(47.6%)といった課題が上位を占めています。
特に深刻なのは、多くの生徒の探究が「調べ学習」のレベルで止まってしまっているという現実です。インターネットで検索した情報をまとめるだけで、自ら問いを立て、仮説を検証し、新たな知見を導き出すという本来の探究プロセスには至っていないケースが多いのです。
生徒が直面する具体的な困難
高校生が探究活動で直面する主な困難として、以下のような点が挙げられます:
- テーマ設定の難しさ:「何を探究すればよいかわからない」という根本的な問題
- データ収集の壁:学術的な情報源へのアクセスや、実験・調査の実施が困難
- 分析力の不足:集めた情報を批判的に分析し、論理的に構成する力が未熟
- 時間的制約:受験勉強との両立で、探究に十分な時間を割けない
- 指導体制の限界:教員側も探究指導の経験が浅く、適切なサポートが難しい
大学が抱く期待と、高校現場の実情のズレ
一方で、大学側は探究学習に大きな期待を寄せています。2024年度入試では、総合型選抜で探究活動を活用した受験生が43.4%に上り、これは一般選抜の3倍以上という高い割合です。関西学院大学の「探究評価型入試」、工学院大学の「探究成果活用型選抜」など、探究活動を直接評価する入試も増加しています。
しかし、大学が期待する「探究力」と、高校生が実際に身につけている能力には大きなギャップが存在します。大学側は以下のような能力を期待していますが、現実はどうでしょうか:
大学が期待する探究力
- 課題発見力:社会や学問領域の中から独自の問題意識を持つ
- 批判的思考力:情報を鵜呑みにせず、多角的に検証する
- 論理的構成力:データに基づいて仮説を立て、検証する
- 創造的解決力:既存の枠組みを超えた新しいアプローチを提案する
- 表現力:研究成果を学術的に適切な形で発表する
高校生の実際のレベル
残念ながら、多くの高校生の探究活動は以下のようなレベルに留まっているのが実情です:
- インターネット検索で得た情報の要約・整理が中心
- 「なぜ?」という問いよりも「何?」という事実確認に終始
- 仮説検証のプロセスが不十分で、結論が表面的
- データの信頼性や出典の検証が不十分
- プレゼンテーションは形式的で、深い考察が不足
なぜギャップが生まれるのか?構造的な要因を分析
このギャップが生まれる背景には、複数の構造的な要因が存在します。
1. 教員の準備不足と多忙化
ESIBLAの調査によると、教員の86.8%が「生徒への評価が難しい」と回答しています。探究学習には教科書もなく、テストによる評価もできません。多くの教員が手探り状態で指導にあたっており、「指導内容に不安が残る」という声も多く聞かれます。
さらに、通常の教科指導に加えて探究指導を行うことで、教員の負担は増大しています。カリキュラム設計、外部連携のコーディネート、個別指導など、探究学習特有の業務が山積みとなっているのです。
2. 時間的制約と受験優先の風潮
高校3年間という限られた時間の中で、本格的な探究活動を行うことは容易ではありません。特に進学校では受験勉強が優先され、探究学習は「やらされ感」を持って取り組まれることも少なくありません。生徒も教員も「探究は受験に直接関係ない」という認識を持ちやすく、深い学びに至らない要因となっています。
3. リソースとネットワークの不足
本格的な探究活動には、専門的な文献へのアクセス、実験設備、外部専門家との連携などが不可欠です。しかし、多くの高校ではこうしたリソースが不足しており、生徒の探究活動は「学校内で完結できる範囲」に限定されがちです。
4. 評価基準の曖昧さ
探究活動の評価は、従来の知識・技能中心の評価とは異なり、プロセスや思考力、態度などを総合的に評価する必要があります。しかし、明確な評価基準が確立されていないため、生徒も「何をどこまでやればよいか」がわからず、表面的な活動に終始してしまうことが多いのです。
大学ができる現実的なアプローチとは
では、このギャップを踏まえて、大学はどのようなアプローチを取るべきでしょうか。過度な期待を抱くのではなく、高校生の現実的なレベルを理解した上で、適切な評価と支援を行うことが重要です。
1. 段階的な評価基準の設定
高校生の探究活動を評価する際は、大学レベルの研究と同じ基準を適用するのではなく、発達段階に応じた評価基準を設定することが重要です。例えば:
- 初級レベル:問題意識を持ち、情報を収集・整理できる
- 中級レベル:仮説を立て、簡単な検証を行える
- 上級レベル:批判的思考を働かせ、独自の見解を示せる
このように段階的な基準を設けることで、生徒の成長プロセスを適切に評価できます。
2. プロセス重視の評価
探究活動の成果だけでなく、「どのように考え、どのように取り組んだか」というプロセスを重視することが大切です。失敗から学んだこと、試行錯誤の過程、協働での気づきなど、結果に表れない学びの価値を評価する視点が必要です。
3. 高大連携による継続的な支援
入試での評価だけでなく、高校段階から大学が積極的に支援することで、探究の質を高めることができます。具体的には:
- 大学教員による出張講義や探究指導
- 大学の研究施設・図書館の開放
- 大学生メンターによる伴走支援
- 探究成果発表会の共同開催
こうした取り組みにより、高校生の探究レベルを段階的に引き上げることが可能になります。
4. 入学後の接続教育の充実
高校での探究経験を大学での学びにスムーズに接続させるため、初年次教育において探究スキルを体系的に育成するプログラムを用意することが重要です。高校での探究が不十分であっても、大学で適切な指導を行えば、学生は急速に成長します。
Study Valley TimeTactによる探究学習の質的向上
こうした課題に対して、テクノロジーを活用した新しいアプローチも登場しています。Study Valleyが提供する探究学習プラットフォーム「TimeTact」は、高校の探究学習が抱える構造的な課題を解決し、生徒の探究の質を向上させる仕組みを提供しています。
TimeTactが実現する3つの価値
1. 豊富な探究テーマと企業連携
TimeTactは100社以上の企業と連携し、300以上の実践的な探究プロジェクトを提供しています。生徒は企業が実際に直面する課題に取り組むことで、社会とつながった本物の探究を体験できます。これにより、「何を探究すればよいかわからない」という根本的な課題を解決します。
2. AIによる個別最適化された支援
2024年にリリースされた「TimeTact探究ロボ」は、探究学習に特化した生成AIです。課題設定から情報収集、整理・分析、まとめ・表現まで、探究の全プロセスにおいて10秒以内にフィードバックを提供。教員の指導負担を95%軽減しながら、生徒一人ひとりに最適化された支援を実現します。
3. 教員の負担軽減と質の向上の両立
専任アドバイザーによる伴走支援、170以上の即活用可能な教材、評価支援ツールなど、教員をサポートする機能が充実。これにより、教員は本来注力すべき「生徒との対話」や「深い学びの促進」に時間を使えるようになります。
大学にとってのメリット
TimeTactを活用している高校の生徒は、以下の点で従来の探究学習とは異なる経験を積んでいます:
- 実社会の課題に基づいた実践的な探究経験
- 企業や専門家からのフィードバックによる質の向上
- デジタルツールを活用した効率的な情報収集・分析
- ポートフォリオによる学習プロセスの可視化
大学の入試担当者は、TimeTactでの活動記録を通じて、生徒の探究プロセスをより詳細に把握できます。また、すでに400校以上で導入されているため、今後ますます多くの受験生がTimeTactを活用した探究経験を持つことになるでしょう。
まとめ:現実を直視し、共に成長する姿勢を
高校生の探究学習のレベルは、大学が期待するほど高くないのが現実です。しかし、これは高校生や教員の努力不足ではなく、構造的な課題に起因するものです。大学関係者には、この現実を受け入れた上で、以下の姿勢が求められます:
- 過度な期待を持たず、発達段階に応じた評価を行う
- 結果だけでなく、プロセスと成長を重視する
- 高大連携により、探究の質向上に積極的に貢献する
- 入学後の接続教育で、探究力をさらに伸ばす
- TimeTactのような新しいツールの活用状況も考慮する
探究学習は、まだ始まったばかりの取り組みです。高校と大学が連携し、テクノロジーも活用しながら、共に試行錯誤を重ねることで、真に探究力を持った次世代の人材育成が可能になるでしょう。大学には、高校の現実を理解し、寄り添いながら共に成長する姿勢が求められているのです。
【記事要約】
高校の探究学習の実態は大学の期待とギャップがあり、9割以上の教員が課題を感じています。多くが調べ学習レベルに留まる中、大学は発達段階に応じた評価と支援が必要です。TimeTactのような新しいツールも活用し、高大連携で探究の質を向上させることが重要です。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。