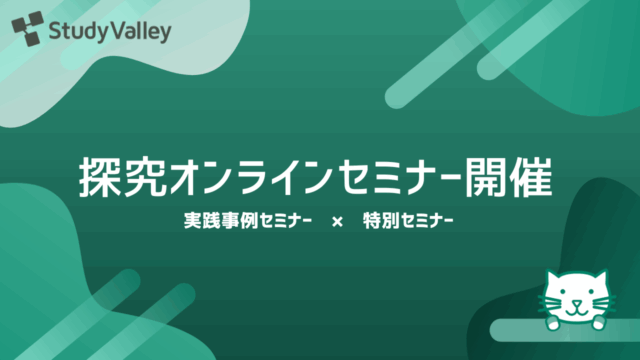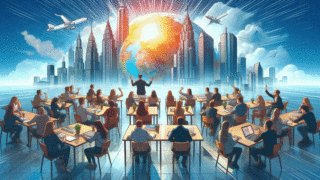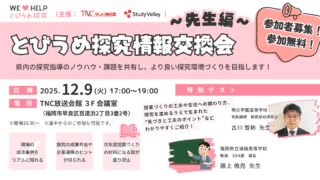なぜ今、大学は「探究力」を持つ学生を求めるのか?
大学入試改革が進む中、多くの大学が「探究力」を持つ学生の獲得に力を入れています。総合型選抜や学校推薦型選抜において、探究活動の実績や探究的な学びの経験を重視する大学が急増しているのです。しかし、なぜ今、大学は「探究力」にこれほど注目するのでしょうか。本記事では、社会の変化、高等教育の転換、そして大学が直面する課題から、「探究力」を持つ学生を求める理由を徹底的に解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
激変する社会が求める「探究力」という新たな能力
21世紀に入り、社会は予測不可能な速度で変化しています。AI・ロボット技術の進展、グローバル化の加速、気候変動、パンデミックなど、私たちは「正解」が存在しない複雑な問題に日々直面しています。このような時代において、大学が育成すべき人材像も大きく変わってきているのです。
VUCAの時代に必要な「問いを立てる力」
VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)と呼ばれる現代社会では、既存の知識を覚えるだけでなく、新たな問いを立て、解決策を模索する力が不可欠です。世界経済フォーラムの「Future of Jobs Report 2023」によると、2027年までに最も重要となるスキルの上位に以下が挙げられています:
- 分析的思考と革新性(Analytical thinking and innovation)
- 能動的学習と学習戦略(Active learning and learning strategies)
- 複雑な問題解決能力(Complex problem-solving)
- 批判的思考と分析(Critical thinking and analysis)
- 創造性・独創性・イニシアチブ(Creativity, originality and initiative)
これらはまさに「探究力」の構成要素そのものです。
知識基盤社会における大学の役割変化
かつて大学は「知識を伝授する場」でした。しかし、インターネットの普及により、知識へのアクセスは容易になり、大学の役割は「知識を活用し、新たな価値を創造する力を育む場」へと変化しています。文部科学省の「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」でも、以下の能力の育成が重視されています:
- 主体的に学び続ける力
- 多様な人々と協働する力
- 新たな価値を創造する力
- 責任ある行動をとる力
高校教育の変革と大学入試への影響
2022年度から高校で本格導入された「総合的な探究の時間」は、生徒が自ら課題を設定し、情報を収集・整理・分析し、まとめ・表現するという一連のプロセスを経験する画期的な教育改革です。この変化は、大学入試や大学教育にも大きな影響を与えています。
探究学習がもたらす学生の質的変化
探究学習を経験した高校生は、従来の受験勉強中心の学習とは異なる能力を身につけています:
- 自己調整学習能力:自ら学習計画を立て、実行し、振り返る力
- 情報リテラシー:膨大な情報から必要なものを選び、批判的に分析する力
- 協働的問題解決能力:多様な人々と協力して課題に取り組む力
- メタ認知能力:自分の思考や学習を客観的に見つめる力
- 表現・発信力:自分の考えを論理的に組み立て、他者に伝える力
大学が直面する「学力の多様化」への対応
探究学習の導入により、高校生の学力は「知識量」から「思考力・判断力・表現力」へと多様化しています。大学は、この新しいタイプの学力を適切に評価し、さらに伸ばしていく必要があります。従来のペーパーテスト中心の入試では測れない能力を持つ学生を見出すため、総合型選抜や学校推薦型選抜の重要性が高まっているのです。
大学が「探究力」を持つ学生を求める5つの理由
では、具体的に大学が「探究力」を持つ学生を求める理由を詳しく見ていきましょう。
1. 大学での学びへの適応力が高い
大学の学びは本来「探究的」なものです。講義を聞くだけでなく、自ら文献を読み、仮説を立て、検証し、論文にまとめるという研究活動は、まさに探究そのものです。高校で探究学習を経験した学生は、このような大学の学びにスムーズに適応できます。
実際、ある国立大学の追跡調査では、探究活動を重視した入試で入学した学生の方が:
- GPA(成績評価平均)が高い傾向にある
- 卒業論文の質が高い
- 大学院進学率が高い
という結果が出ています。
2. 主体的な学習者として成長する可能性が高い
「探究力」を持つ学生は、与えられた課題をこなすだけでなく、自ら問いを立て、学びを深めていく主体性を持っています。これは、大学が目指す「自律的学習者」の育成において極めて重要な資質です。
3. 研究活動への貢献が期待できる
大学は教育機関であると同時に研究機関でもあります。探究力を持つ学生は、早い段階から研究活動に参加し、新たな発見や知見の創出に貢献する可能性が高いのです。特に、学部生の段階から研究に参加する機会が増えている現在、この点は重要です。
4. 多様性がイノベーションを生む
探究学習では、生徒一人ひとりが異なるテーマに取り組みます。この経験により、多様な視点や価値観を持つ学生が大学に集まることで、キャンパス全体の知的活性化とイノベーションの創出が期待できます。
5. 社会が求める人材の育成につながる
企業や社会が求める「課題発見・解決能力」「創造性」「協働性」などは、まさに探究活動を通じて培われる能力です。探究力を持つ学生を受け入れ、さらにその能力を伸ばすことで、社会に貢献できる人材を輩出できます。
探究力を評価し、育てるための大学の取り組み
多くの大学が、探究力を持つ学生を適切に評価し、その能力をさらに伸ばすための取り組みを始めています。
入試における探究力の評価方法
- 探究活動報告書の評価:活動の内容だけでなく、プロセスや学びを重視
- プレゼンテーション審査:探究成果を論理的に説明する力を評価
- グループディスカッション:協働的問題解決能力を見る
- ポートフォリオ評価:継続的な学びの記録から成長を評価
入学後の探究力育成プログラム
- 初年次セミナーの充実:大学での探究的学びへの導入
- PBL(Project-Based Learning)の導入:実社会の課題に取り組む授業
- 学部横断型プログラム:分野を超えた探究活動の促進
- 早期研究室配属:1・2年次から研究活動に参加する機会
- 海外研修・インターンシップ:グローバルな視点での探究活動
Study Valley TimeTactが実現する探究力の可視化と育成支援
大学が探究力を持つ学生を求める一方で、「どのように探究力を評価すればよいか」「高校での探究活動をどう把握すればよいか」という課題を抱えています。Study Valley TimeTactは、これらの課題を解決し、大学と高校の効果的な連携を支援します。
大学向けTimeTactの主要機能
- 探究活動の詳細な記録閲覧:生徒の探究プロセスを時系列で把握
- 評価基準の標準化ツール:探究力を客観的に評価するルーブリック
- 高校との連携プラットフォーム:探究テーマのマッチングや共同プログラムの管理
- 入学後の追跡調査機能:探究入試で入学した学生の成長を分析
- データ分析レポート:探究力と大学での成績・活動の相関を可視化
導入大学の成果
「TimeTactを導入してから、探究活動の評価が格段に効率化されました。特に、生徒の成長プロセスが可視化されることで、本当に探究力のある学生を見極められるようになりました」(私立大学アドミッションオフィス)
「高校との連携が深まり、大学の求める人材像を高校側に正確に伝えられるようになりました。結果として、ミスマッチが減少し、入学後の学生満足度も向上しています」(国立大学入試課)
まとめ:探究力が拓く大学教育の新たな地平
大学が「探究力」を持つ学生を求める理由は、単に入試のトレンドではありません。変化の激しい社会において、主体的に学び、新たな価値を創造できる人材を育成することは、大学の社会的使命なのです。
探究力を持つ学生は、大学での学びを最大限に活用し、研究活動に貢献し、卒業後も社会で活躍する可能性が高い。だからこそ、大学は今、「探究力」に注目し、そのような学生の獲得と育成に力を入れているのです。
高校教育の変革と歩調を合わせ、大学も変わる必要があります。Study Valley TimeTactは、その変革を支援し、探究力を持つ学生と大学の最適なマッチングを実現します。未来を担う人材の育成に向けて、今こそ大学は「探究力」を軸とした新たな教育の形を構築する時なのです。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。