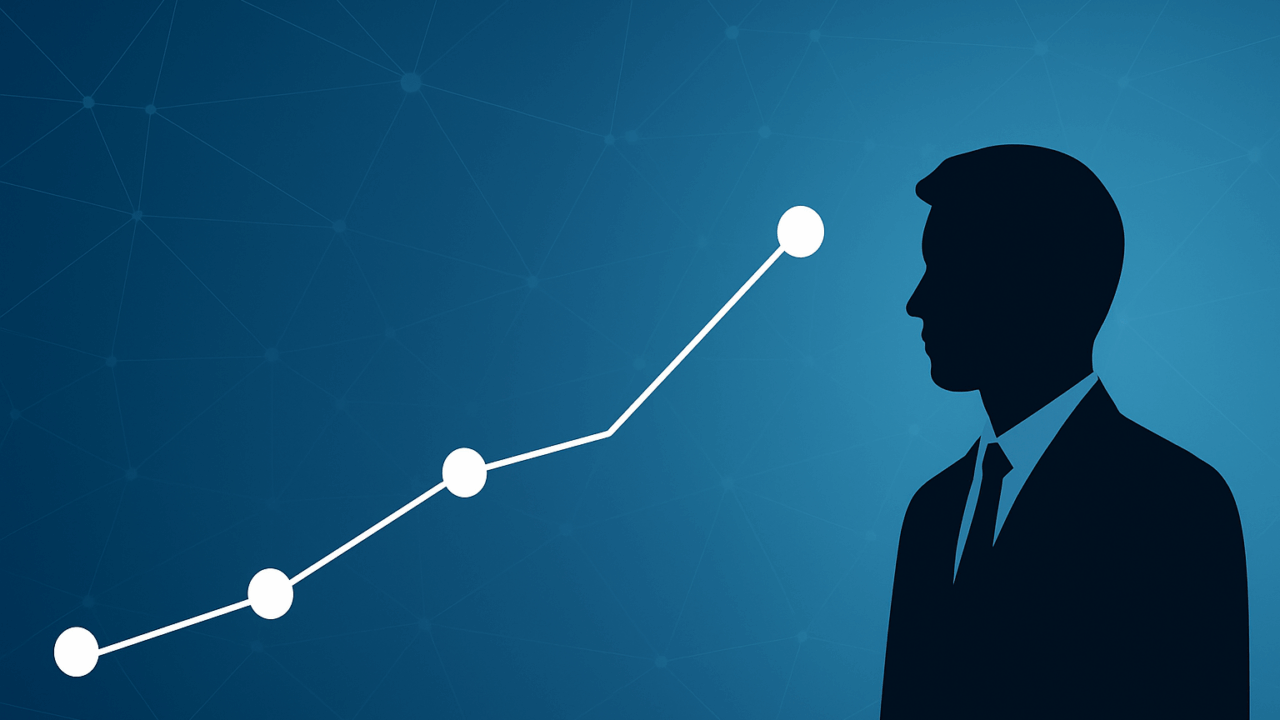「採用」という”点”でなく、「育成」という”線”で捉える。これからの人材獲得競争
労働人口の減少が進む中、企業の人材獲得競争は年々激化しています。しかし、多くの企業は依然として「採用」という一時点にばかり注力し、長期的な人材育成の視点を欠いているのが現状です。これからの時代、大学4年生になってから初めて学生と接触するような従来型の採用活動では、優秀な人材の獲得は困難になるでしょう。本記事では、「採用」を点ではなく「育成」という線で捉え、高校段階から未来の人材と関係を構築する新しい人材獲得戦略について解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
従来型採用活動の限界と新たな課題
日本経済団体連合会の調査によると、2024年度の新卒採用において「計画通りの人数を確保できなかった」と回答した企業は全体の68%に上ります。特に中小企業においては、この数値は82%にまで達しており、従来の採用手法では優秀な人材の確保が極めて困難になっていることが明らかです。
なぜ従来型の採用活動は限界を迎えているのか
現在の採用市場が直面している課題は以下の通りです:
- 接触時期の遅さ:大学3年生からの接触では、すでに他社に興味を持たれている
- 画一的なアプローチ:ナビサイトや合同説明会では差別化が困難
- 短期的な関係構築:数回の面接では相互理解が不十分
- ミスマッチの増加:入社3年以内の離職率は約30%で高止まり
- 採用コストの高騰:1人あたりの採用コストは平均93.6万円(2023年度)
Z世代の価値観の変化がもたらす影響
さらに、Z世代と呼ばれる若者たちの価値観の変化も、従来型採用の限界を加速させています:
- キャリアの自律性重視:会社に依存しない、自己成長を重視する傾向
- 社会的意義の追求:給与や福利厚生よりも、仕事の社会的インパクトを重視
- 透明性の要求:企業文化や働き方の実態を事前に知りたがる
- 長期的な関係性:一方的な選考ではなく、相互理解のプロセスを求める
「育成」という線で捉える新しい人材獲得戦略
これらの課題を解決するためには、採用を「点」ではなく「線」として捉え直す必要があります。つまり、大学生になってから初めて接触するのではなく、高校段階から長期的な関係を構築し、共に成長していく戦略への転換です。
高校段階からの関係構築がもたらすメリット
早期からの関係構築には、以下のような具体的なメリットがあります:
- 相互理解の深化
- 長期間の接触により、企業文化や価値観の深い理解が可能
- 学生の成長過程を見守ることで、真の能力や適性を把握
- ミスマッチの削減
- 早期離職率の大幅な低下(導入企業では10%以下の事例も)
- 入社前の期待値調整により、リアリティショックを軽減
- 採用コストの最適化
- 長期的には採用単価の低下
- 教育投資としての位置づけによる費用対効果の向上
- 企業ブランディング効果
- 教育に貢献する企業としての社会的評価向上
- 口コミによる自然な認知度拡大
探究学習を通じた実践的な関係構築
特に注目すべきは、高校で必修化された「総合的な探究の時間」の活用です。年間70時間以上の探究活動を通じて、企業は実践的な形で高校生と関わることができます。
具体的な関わり方の例:
- 課題提供型連携:企業が抱える実際の課題を探究テーマとして提供
- メンター派遣:社員が定期的に高校を訪問し、探究活動をサポート
- インターンシップ受入:短期の職場体験から長期のプロジェクト参加まで
- 成果発表会への参加:生徒の成長を見守り、フィードバックを提供
成功企業の事例から学ぶ実践方法
すでに一部の先進的な企業は、この「育成型人材獲得戦略」を実践し、成果を上げています。
事例1:製造業A社の5年計画
従業員数約3,000名の製造業A社は、2019年から地元高校との連携を開始:
- 1年目:工場見学と出張授業から開始(3校・約200名)
- 2年目:探究学習のテーマ提供とメンター派遣(5校・約100名)
- 3年目:サマーインターンシップの実施(20名)
- 4年目:大学進学後も継続的にフォロー
- 5年目:プログラム参加者から初の新卒採用(5名)
成果:採用した5名全員が3年後も在籍(離職率0%)、採用コストは従来の約60%に削減
事例2:IT企業B社のオープンイノベーション型
従業員数約500名のIT企業B社は、高校生の探究活動を通じてイノベーションを創出:
- 高校生向けアプリ開発コンテストを主催
- 優秀作品は実際にサービス化を検討
- 参加者にはメンタリングと技術サポートを提供
- 大学進学後もコミュニティで関係を維持
成果:3年間で参加者から12名を採用、うち2名は入社2年目で新規事業を立ち上げ
事例3:地方企業C社の地域密着型
従業員数約100名の地方企業C社は、地域の高校と包括連携協定を締結:
- 年間を通じた探究学習支援プログラムを提供
- 地域課題解決をテーマに産学連携PBLを実施
- 優秀な生徒には奨学金制度も用意
- Uターン就職を前提とした長期的な関係構築
成果:地元出身者の採用率が50%から80%に向上、定着率も95%以上を維持
育成型人材獲得戦略の実装ステップ
では、具体的にどのように始めればよいのでしょうか。以下に、段階的な実装ステップを示します。
Phase 1:準備期(1-3ヶ月)
- 社内体制の構築
- 人事部門と事業部門の連携体制確立
- 教育CSR担当者の任命
- 予算の確保(採用予算の一部を振り分け)
- プログラムの設計
- 自社の強みを活かせる教育コンテンツの開発
- 高校生にとって魅力的なテーマの設定
- 評価指標(KPI)の設定
Phase 2:パイロット期(6-12ヶ月)
- 小規模での試行
- 1-2校との連携から開始
- 出張授業や工場見学など、負担の少ない活動から
- 参加生徒と社員の反応を詳細に記録
- 関係性の構築
- 学校との信頼関係を醸成
- 教員との定期的な情報交換
- 生徒の反応を踏まえたプログラムの改善
Phase 3:拡大期(1-2年)
- プログラムの本格展開
- 連携校を5-10校に拡大
- 探究学習への本格的な参画
- インターンシップの受け入れ開始
- 継続的な関係維持
- 卒業生とのネットワーク構築
- 大学進学後のフォローアップ
- SNSやコミュニティでの交流継続
Phase 4:成果創出期(3年目以降)
- 採用への接続
- プログラム参加者からの採用開始
- 通常採用との差別化(特別選考ルートなど)
- 入社後のフォローアップ体制構築
- 効果測定と改善
- 定着率、活躍度合いの測定
- ROIの算出と経営層への報告
- プログラムの継続的改善
Study Valley TimeTactによる効率的な実装支援
このような育成型人材獲得戦略を実装する際、最大の課題は「どのように効率的に多数の高校・生徒と関係を構築し、管理するか」という点です。Study Valley TimeTactは、この課題を解決するための統合プラットフォームを提供しています。
TimeTactが提供する企業向け機能
- マッチング機能:企業の課題と高校の探究テーマを自動でマッチング
- コミュニケーション機能:生徒・教員との円滑なやり取りを支援
- 進捗管理機能:複数校・複数プロジェクトを一元管理
- 人材データベース:関わった生徒の成長記録を長期的に蓄積
- 効果測定機能:投資対効果を可視化するダッシュボード
導入企業の声
「TimeTactを導入してから、10校以上との連携が可能になりました。特に、生徒一人ひとりの成長過程を記録できる機能は、将来の採用を見据えた関係構築に非常に有効です。」(製造業・人事部長)
「探究学習の支援を通じて、高校生の新鮮な視点から多くの気づきを得ています。単なる採用活動ではなく、企業としての成長にもつながっています。」(IT企業・経営企画部)
まとめ:今すぐ始めるべき理由
「採用」を点ではなく「育成」という線で捉える新しい人材獲得戦略は、もはや一部の先進企業だけの取り組みではありません。少子化が進む中、従来型の採用活動に固執する企業は、5年後、10年後に深刻な人材不足に直面することになるでしょう。
一方で、今から高校生との関係構築を始める企業は、優秀な人材との長期的な信頼関係を築き、持続的な競争優位を確立できます。重要なのは、完璧なプログラムを作ることではなく、まず一歩を踏み出すことです。小さな取り組みから始めて、徐々に拡大していけばよいのです。
未来の人材獲得競争を勝ち抜くために、今こそ「育成」という視点での人材戦略を始めてみませんか。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。