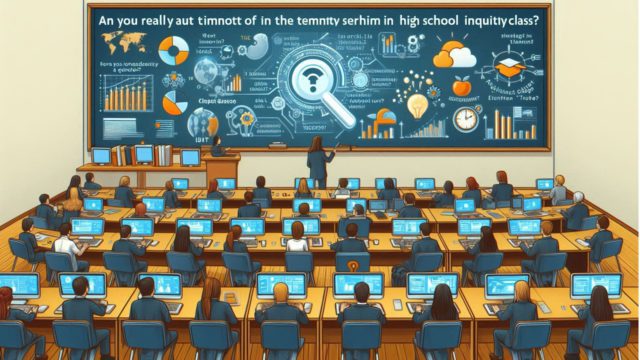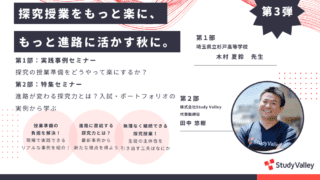企業の持つアセット(資源)を教育に。工場見学や社員インタビューが探究の教材になる
多くの企業が「教育支援をしたいが、何から始めればよいか分からない」と悩んでいます。しかし実は、企業が日常的に保有している施設、人材、技術、ノウハウこそが、高校生の探究学習にとって最高の教材となるのです。特別な準備や新たな投資は必要ありません。本記事では、企業が既に持っているアセットを活用して、効果的な教育支援を実現する方法と、それがもたらす企業側のメリットについて詳しく解説します。
を教育に。工場見学や社員インタビューが探究の教材になる-1024x574.png)
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
企業アセットが教育現場で求められる理由
2022年度から全国の高等学校で必修化された「総合的な探究の時間」では、生徒たちは実社会の課題に取り組むことが求められています。しかし、学校内だけでは「リアルな社会」を体験することには限界があり、企業の持つ「本物」の資源への期待が高まっています。
教科書では学べない「生きた教材」の価値
高校の探究学習において、生徒たちは以下のような学びを必要としています:
- 実際の社会課題とその解決プロセス
- 最新の技術やイノベーションの現場
- 働く人々の生の声と職業観
- 企業活動が社会に与える影響とその責任
これらは、企業の日常業務の中に当たり前のように存在している要素です。企業にとっては「普通」のことでも、高校生にとっては新鮮で刺激的な学びの機会となります。
探究学習が求める「本物体験」
文部科学省の学習指導要領では、探究学習において「実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立てる」ことが重視されています。この「実社会や実生活」との接点こそ、企業が提供できる最大の価値です。
例えば、環境問題について探究する生徒にとって、実際の工場での省エネ取り組みを見学したり、環境担当者から直接話を聞いたりすることは、インターネットで調べる情報とは比較にならない深い学びをもたらします。
活用できる企業アセット5つのカテゴリー
企業が教育支援に活用できるアセットは、大きく5つのカテゴリーに分類できます。それぞれの特徴と活用方法を見ていきましょう。
1. 施設・設備アセット
工場、研究所、オフィス、店舗など、企業が保有する施設は、そのまま学びの場となります。
活用例:
- 製造工場:生産工程の見学、品質管理の実際、安全対策の学習
- 研究開発施設:最新技術の体験、研究員との対話、実験デモンストレーション
- 物流センター:サプライチェーンの理解、効率化の工夫、AI活用の現場
- 本社オフィス:企業文化の体感、各部門の役割理解、会議室でのワークショップ
これらの施設見学は、単なる「見て回る」だけでなく、生徒の探究テーマに応じてカスタマイズすることで、より深い学びにつながります。
2. 人的アセット
社員一人ひとりが持つ専門知識と経験は、最も価値ある教育資源です。
活用例:
- 専門家による講義:技術者、研究者、マーケターなどによる専門分野の解説
- キャリアインタビュー:様々な職種の社員による仕事内容と職業観の共有
- メンタリング:探究活動への継続的なアドバイスとフィードバック
- 若手社員との交流:年齢の近い先輩としてのロールモデル提示
社員の参加は、CSR活動としてだけでなく、社員自身の成長機会にもなります。高校生に分かりやすく説明することで、自身の仕事を振り返る良い機会となります。
3. 技術・ノウハウアセット
企業が蓄積してきた技術やノウハウは、探究学習の題材として最適です。
活用例:
- 特許技術の解説:イノベーションが生まれた背景と社会への影響
- 品質管理手法:PDCAサイクルの実践的な理解
- マーケティング戦略:市場調査から商品開発までのプロセス
- プロジェクト管理:チームワークと目標達成の方法論
企業秘密に配慮しながらも、基本的な考え方や手法を教育用にアレンジすることで、生徒たちに実践的な学びを提供できます。
4. データ・情報アセット
企業が保有するデータや事例は、探究活動の貴重な一次資料となります。
活用例:
- 環境データ:CO2削減の実績、省エネルギーの取り組み結果
- 社会貢献活動の記録:地域連携の事例、ボランティア活動の成果
- 顧客の声:商品・サービスへのフィードバックと改善事例
- 失敗事例:課題に直面した際の対応と学び(教育的価値が高い)
生のデータに触れることで、生徒はデータ分析の重要性と難しさを実感できます。
5. ネットワークアセット
取引先、業界団体、地域とのつながりも、教育支援に活用できる重要な資源です。
活用例:
- サプライチェーン見学:原材料調達から最終消費者までの流れ
- 業界団体との連携:業界全体の課題と取り組みの紹介
- 海外拠点との交流:グローバル視点での課題理解
- 地域企業との共同プログラム:地域経済の仕組みと相互依存関係
効果的な教育プログラムの設計と実施方法
企業アセットを活用した教育支援を成功させるには、適切な設計と準備が必要です。以下、実施のポイントを解説します。
事前準備:学校との連携と目的の明確化
効果的なプログラムを実施するために、以下の点を事前に確認します:
- 生徒の探究テーマと学習目標の把握
- 参加人数と実施時期の調整
- 安全管理と保険関係の確認
- 撮影・記録に関する許諾
特に重要なのは、単発のイベントで終わらせず、探究学習の流れに位置づけることです。事前学習→企業での体験→事後の振り返りという一連の流れを設計することで、学びの効果が格段に高まります。
実施時の工夫:双方向性と主体性の重視
高校生の学びを最大化するための実施上の工夫:
- 一方的な説明ではなく、対話形式を重視
- 生徒からの質問時間を十分に確保
- ワークショップやグループディスカッションの導入
- 実際に手を動かす体験活動の組み込み
例えば、工場見学では、ただ見るだけでなく、「改善提案を考える」というミッションを与えることで、生徒の観察力と思考力を引き出すことができます。
フォローアップ:継続的な関係構築
一度の体験で終わらせず、継続的な学びの支援を行うことが重要です:
- メールやオンラインでの質問対応
- 探究成果発表会への参加とフィードバック
- 優秀な探究成果の社内共有
- 次年度以降の改善に向けた振り返り
企業が得られる5つのメリット
教育支援は社会貢献活動として重要ですが、同時に企業にも多くのメリットをもたらします。
1. 未来の人材との早期接点構築
高校生との交流は、将来の採用候補者との早期の関係構築につながります。企業理念や事業内容を深く理解した学生が、数年後に入社を希望するケースも少なくありません。
2. 社員のモチベーション向上
高校生への指導を通じて、社員自身が仕事の意義を再確認する機会となります。「なぜこの仕事をしているのか」を改めて考え、言語化することで、日常業務へのモチベーションも向上します。
3. 新たな視点とイノベーションの種
高校生の素朴な疑問や斬新なアイデアが、企業に新たな気づきをもたらすことがあります。固定観念にとらわれない若い世代の視点は、イノベーションのヒントとなる可能性を秘めています。
4. 地域社会での信頼構築
地域の教育に貢献することで、企業の社会的信頼が向上します。これは、地域での事業展開や人材確保にも好影響をもたらします。
5. ESG経営の実践と発信
教育支援はESGのS(社会)領域における具体的な取り組みとして、投資家や取引先にアピールできます。特に人的資本への投資として評価される傾向が強まっています。
Study Valley TimeTactで実現する効率的な連携
企業の教育支援を効果的に実施するには、学校との調整や実施内容の管理など、多くの事務作業が発生します。Study Valley TimeTactは、こうした課題を解決し、企業と学校の連携を円滑にするプラットフォームです。
マッチング機能で最適な連携先を発見
TimeTactの企業・学校マッチング機能により、企業は自社のアセットや支援可能な内容を登録するだけで、ニーズの合う学校とつながることができます。探究テーマや地域、実施時期などの条件で絞り込みが可能なため、効率的な連携先の発見が可能です。
プログラム管理の一元化
実施スケジュール、参加者リスト、事前事後の資料共有などを一元管理できます。複数の学校と連携する場合でも、それぞれの進捗状況を把握しやすく、担当者の負担を大幅に軽減します。
実施効果の可視化とレポート生成
生徒からのフィードバックや学習成果を自動的に集計・分析し、教育支援の効果を可視化します。これにより、社内での活動報告やESGレポートへの記載も容易になります。
継続的な関係構築のサポート
一度連携した学校との継続的なコミュニケーションをサポートします。次年度の計画立案や、他校への横展開なども効率的に行えるため、教育支援活動の持続的な発展が可能です。
まとめ:今すぐ始められる教育支援
企業の持つアセットは、そのまま高校生の探究学習にとって貴重な教材となります。工場、社員、技術、データ、ネットワークといった既存の資源を活用することで、特別な投資をすることなく、効果的な教育支援を始めることができます。
重要なのは、「完璧な準備ができてから」ではなく、「できることから始める」という姿勢です。小規模な工場見学や、1人の社員による出前授業からでも構いません。Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用すれば、効率的に学校と連携し、継続的な教育支援を実現できます。
教育支援は、未来の人材育成への投資であると同時に、企業自身の成長機会でもあります。今こそ、企業の持つ「当たり前」を、高校生の「特別な学び」に変える時です。一歩踏み出すことで、企業と教育の新たな連携の形が見えてくるはずです。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。

を教育に。工場見学や社員インタビューが探究の教材になる.jpg)