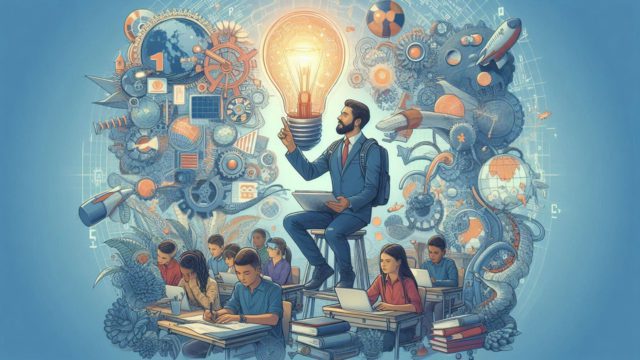「総合的な探究の時間」をビジネスチャンスに。教育現場のニーズと企業のシーズを繋ぐ方法
2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」。年間約70時間、全国約330万人の高校生が取り組むこの授業は、企業にとって新たなビジネスチャンスの宝庫となっています。しかし、多くの企業は「教育現場とどう関わればいいのか」「ビジネスとして成立するのか」という疑問を抱えています。本記事では、教育現場の切実なニーズと企業が持つシーズをマッチングさせ、社会貢献とビジネスを両立させる具体的な方法を解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
「総合的な探究の時間」が生み出す巨大な教育市場の実態
まず、「総合的な探究の時間」がいかに大きな市場となっているかを数字で見てみましょう。文部科学省の統計によると、2024年現在、全国の高校生約330万人が年間70時間の探究学習に取り組んでいます。これは延べ2億3,100万時間という膨大な学習時間です。
教育現場が直面する3つの深刻な課題
1. 教材・コンテンツ不足の危機
日本教育新聞の調査では、探究学習を担当する教員の87%が「適切な教材やコンテンツが不足している」と回答。多くの学校では、教員が手作りで教材を作成しており、その準備時間は月平均20時間を超えています。質の高い教材へのニーズは極めて高い状況です。
2. 専門知識・外部講師の不足
生徒の探究テーマは多岐にわたり、環境問題からAI技術、地域活性化まで幅広い分野に及びます。しかし、学校の教員だけでこれらすべてに対応することは不可能です。全国高等学校長協会の調査では、92%の学校が「外部専門家との連携を希望」しています。
3. 評価・管理システムの欠如
探究学習は従来の教科学習と異なり、生徒一人ひとりが異なるテーマに取り組みます。その進捗管理や評価は極めて複雑で、多くの学校がエクセルでの管理に限界を感じています。デジタルツールへの需要が急速に高まっています。
市場規模と成長性
- 現在の市場規模:約500億円(教材、外部講師、システム等を含む)
- 年間成長率:15-20%(2022-2024年実績)
- 2030年予測:1,500億円規模に成長見込み
- 参入企業数:2022年の約200社から2024年には500社超に急増
企業が持つシーズを教育現場のニーズに変換する5つのアプローチ
では、企業はどのようにして自社のシーズ(技術・知見・リソース)を教育現場のニーズに合わせて提供し、ビジネスとして成立させることができるのでしょうか。成功事例をもとに、5つのアプローチを紹介します。
アプローチ1:専門知識のパッケージ化
企業が持つ専門知識を、高校生向けの探究教材としてパッケージ化する方法です。単なる企業紹介ではなく、社会課題の解決プロセスを学べる教材として設計することがポイントです。
成功事例:大手化学メーカーA社
- 自社の環境技術を「海洋プラスチック問題を解決する探究プログラム」として教材化
- 実験キット付きで1セット5万円で提供
- 初年度300校が導入、売上1.5億円を達成
- 副次効果として、理系志望者からの認知度が40%向上
アプローチ2:社員派遣型メンタリングサービス
社員を探究学習のメンターとして派遣し、生徒の課題解決をサポートするサービスです。社員教育と社会貢献を兼ねた戦略的CSRとして位置づけることで、持続可能なビジネスモデルを構築できます。
成功事例:IT企業B社
- 若手エンジニアを月2回、高校に派遣
- プログラミングやデータ分析の探究をサポート
- 学校側は年間30万円のサポート費用を支払い
- 社員の定着率が15%向上、採用広報効果も
アプローチ3:探究学習プラットフォームの開発・運営
探究学習の進捗管理や評価を効率化するデジタルプラットフォームを開発・提供する方法です。SaaS型のビジネスモデルで、安定的な収益を確保できます。
成功事例:EdTechベンチャーC社
- 探究学習管理システムを月額3万円/校で提供
- 生徒の活動記録、ポートフォリオ作成、評価機能を搭載
- 2年で1,000校が導入、年間売上3.6億円
- 大学入試での活用も広がり、さらなる成長見込み
アプローチ4:リアルな企業課題の教材化
企業が実際に直面している課題を、高校生向けのPBL(Project Based Learning)教材として提供する方法です。課題解決のアイデアを企業の新規事業に活用するWin-Winモデルです。
成功事例:食品メーカーD社
- 「フードロス削減の新商品開発」を探究テーマとして提供
- 優秀なアイデアは実際に商品化を検討
- 参加費として1校あたり10万円を設定
- 高校生のアイデアから2つの新商品が誕生、売上5億円
アプローチ5:探究学習コンサルティングサービス
学校全体の探究カリキュラム設計や教員研修を提供するコンサルティングサービスです。単発ではなく年間契約での継続的な支援により、安定収益を確保できます。
成功事例:教育コンサルE社
- 年間100万円で探究カリキュラムの設計・運営支援
- 教員研修、外部講師アレンジ、評価設計まで包括サポート
- 50校と契約、年間売上5,000万円
- 学校の探究実績向上により、リピート率95%
教育現場と企業を効果的に繋ぐ実践的な方法論
企業が教育現場と連携を始める際、最初の一歩をどう踏み出せばよいのでしょうか。成功企業の事例から導き出された、効果的な方法論を紹介します。
ステップ1:教育現場の文化と制約を理解する
学校には独特の文化や制約があります。これらを理解せずにアプローチすると、せっかくの提案も受け入れられません。
押さえるべきポイント:
- 年間スケジュール:4月に年間計画が決まるため、前年度2-3月のアプローチが効果的
- 予算サイクル:公立校は年度予算制のため、柔軟な価格設定が必要
- 意思決定プロセス:担当教員→教科主任→教頭→校長の承認フローを理解
- 教育的価値の重視:営業色を出さず、教育効果を前面に
ステップ2:小規模パイロットから始める
いきなり大規模展開を狙うのではなく、まずは1-2校でのパイロット実施から始めることが成功の鍵です。
パイロット実施のメリット:
- 現場のフィードバックを受けてサービスを改善できる
- 成功事例を作ることで、他校への展開が容易に
- 教員ネットワークでの口コミ効果が期待できる
- 初期投資を抑えてリスクを最小化できる
ステップ3:教育委員会との連携を構築
個別の学校へのアプローチも重要ですが、教育委員会との連携により、地域全体での導入が可能になります。
教育委員会連携のアプローチ:
- 地域の教育課題解決に貢献する提案を準備
- 複数校での一括導入による割引プランを提示
- 教員研修プログラムとセットで提案
- 地域企業との連携による地域活性化をアピール
ステップ4:持続可能な価格設定とビジネスモデル
教育現場の予算制約を考慮しつつ、ビジネスとして成立する価格設定が重要です。
効果的な価格戦略:
- フリーミアムモデル:基本機能は無料、高度な機能は有料
- 段階的価格設定:生徒数に応じた柔軟な価格体系
- パッケージ化:教材+研修+サポートのセット販売
- 成果報酬型:探究の成果(大学合格等)に応じた報酬
Study Valley TimeTactが実現する、企業と教育現場の最適なマッチング
企業が教育現場との連携を成功させるためには、両者のニーズを的確にマッチングさせるプラットフォームが不可欠です。Study Valley TimeTactは、まさにこの課題を解決するために開発されました。
TimeTactが提供する3つの価値
1. 教育現場のニーズの可視化
TimeTactには全国の高校の探究学習データが蓄積されており、どの学校がどのような分野の支援を必要としているかが一目でわかります。企業は自社のシーズに合った学校を効率的に見つけることができます。
2. マッチングの自動化と最適化
AIを活用した自動マッチング機能により、企業の提供可能なリソースと学校のニーズを最適な形で結びつけます。これにより、営業コストを大幅に削減しながら、成約率を向上させることができます。
3. 成果の可視化とPDCA支援
連携後の探究学習の成果をデータで可視化し、企業は自社の貢献度を定量的に把握できます。これにより、サービスの改善や新たな提案に繋げることが可能です。
TimeTact活用企業の実績
- 製造業F社:TimeTact経由で50校と連携、探究教材の売上2億円達成
- サービス業G社:社員メンター派遣で30校と契約、若手社員の離職率30%改善
- IT企業H社:探究データ分析サービスで100校導入、年間売上1億円
まとめ:教育への投資が生み出す、企業の新たな成長戦略
「総合的な探究の時間」は、単なるCSR活動の場ではなく、企業にとって大きなビジネスチャンスです。教育現場の切実なニーズに応える形で自社のシーズを提供することで、社会貢献とビジネス成長を両立させることができます。重要なのは、教育現場の文化を理解し、段階的にアプローチすること。そして、Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用して、効率的にマッチングを実現することです。今こそ、教育市場への参入を検討する絶好のタイミングと言えるでしょう。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。