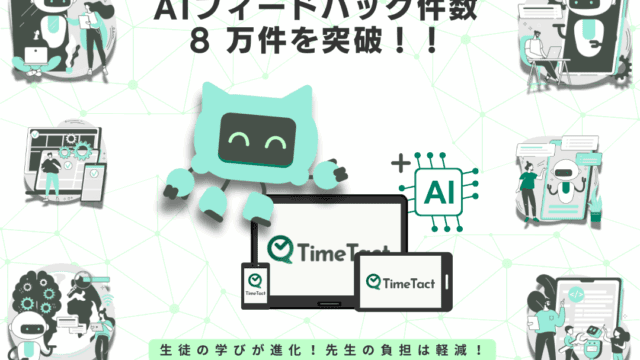「とりあえずSDGs」から脱却。生徒が”自分ごと”として社会課題を捉えるには
「先生、探究のテーマが決まりません」「じゃあ、SDGsから選んでみたら?」――このような会話が、全国の高校で繰り返されています。確かにSDGsは重要な社会課題の枠組みですが、生徒にとっては遠い世界の話に感じられ、結局インターネットで調べた情報をまとめるだけの「調べ学習」に終わってしまいます。本記事では、生徒が社会課題を「自分ごと」として捉え、真の探究活動へと発展させる具体的な指導方法を解説します。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
なぜ「とりあえずSDGs」が生まれてしまうのか
多くの学校で、探究学習のテーマ設定においてSDGsが安易に選ばれる背景には、教員側と生徒側それぞれの事情があります。
教員側の事情:指導の「型」への依存
SDGsは17の目標と169のターゲットという明確な枠組みがあるため、教員にとっては指導しやすい素材です。しかし、この「わかりやすさ」が逆に落とし穴となっています。
- 「17の目標から選ばせれば、とりあえずテーマは決まる」という安心感
- 教材や資料が豊富にあり、準備の負担が少ない
- 「社会的に意義のあるテーマ」という大義名分が得られる
- 評価基準が設定しやすい(SDGsへの理解度で測れる)
生徒側の事情:社会課題との距離感
一方、生徒にとってSDGsの多くのテーマは、自分の日常生活からかけ離れた「教科書の中の話」として認識されがちです。
- 「貧困をなくそう」と言われても、実感が湧かない
- 「気候変動に具体的な対策を」と言われても、個人でできることが見えない
- グローバルな視点を求められても、ローカルな実体験が不足している
- 「正解」を求める学習習慣から、「問い」を立てる思考への転換ができない
結果として生まれる「形だけの探究」
このような状況下では、生徒の探究活動は以下のような表面的なものになりがちです:
- SDGsの目標を選ぶ(例:目標14「海の豊かさを守ろう」)
- インターネットで「海洋プラスチック問題」を検索
- 見つけた情報をまとめてポスターやスライドを作成
- 「プラスチックを減らしましょう」という一般論で締めくくる
これでは、探究ではなく単なる「調べ学習」であり、生徒の成長にはつながりません。
社会課題を「自分ごと」にする5つのアプローチ
では、どうすれば生徒が社会課題を自分の問題として捉え、主体的に探究できるようになるのでしょうか。以下、具体的な5つのアプローチを紹介します。
1. 半径5メートルから始める「身近な違和感」の発見
社会課題は遠い世界の話ではなく、生徒の日常生活の中にも必ず存在します。まずは身の回りの小さな違和感や疑問から始めることが重要です。
- 学校生活の中で:「なぜ給食の残飯が多いのか」「制服のルールは誰のためにあるのか」
- 地域の中で:「駅前の商店街がシャッター街になっている理由」「公園で遊ぶ子どもが減った背景」
- 家庭生活の中で:「祖父母との会話が少ない理由」「きょうだい間の教育機会の差」
これらの身近な問題から出発し、徐々に視野を広げていくことで、SDGsとの接続も自然に見えてきます。
2. 当事者の声を聞く「フィールドワーク」の実施
インターネットの情報だけでは、社会課題の実態は見えてきません。実際に現場に足を運び、当事者の声を聞くことで、問題が「自分ごと」になります。
- 高齢者施設を訪問し、デジタルデバイドの実態を知る
- 地元の農家にインタビューし、後継者不足の深刻さを実感する
- 外国人労働者と対話し、共生社会の課題を理解する
- 障害者スポーツの現場を見学し、バリアフリーの現状を学ぶ
3. 自分の「好き」や「得意」との接続
生徒が情熱を持って取り組める探究にするには、個人の興味関心や特技と社会課題を結びつけることが効果的です。
- スポーツ好きな生徒:「部活動の地域格差」「スポーツを通じた多世代交流」
- SNSが得意な生徒:「デジタルネイティブ世代の情報リテラシー」「オンラインいじめの防止」
- 料理が好きな生徒:「フードロスの削減」「地産地消の推進」
- ゲーム好きな生徒:「ゲーミフィケーションを活用した社会課題解決」
4. 「もし自分が○○だったら」という想像力の活用
共感力を育てるために、異なる立場に立って考える思考実験を取り入れます。
- 「もし自分が車椅子ユーザーだったら、この街はどう見えるか」
- 「もし自分が外国人留学生だったら、どんな困りごとがあるか」
- 「もし自分が認知症の高齢者の家族だったら、何が必要か」
- 「もし自分が10年後の市長だったら、どんな政策を実行するか」
5. 小さな実践から始める「アクションリサーチ」
調査や分析だけでなく、実際に行動を起こしてその結果を検証することで、社会課題への当事者意識が生まれます。
- 校内でフードドライブを企画・実施し、食品ロスの実態を体感
- 地域の清掃活動を通じて、ゴミ問題の深刻さを実感
- 高齢者向けスマホ教室を開催し、デジタルデバイドの解消に貢献
- 学校周辺のバリアフリーマップを作成し、改善提案を行う
「自分ごと化」を促進する教員の関わり方
生徒が社会課題を自分ごととして捉えるためには、教員の適切な支援が不可欠です。
問いかけの工夫:「なぜ?」から「どうして私は?」へ
一般的な問いかけから、個人的な関心や経験に結びつく問いかけへとシフトします。
- ❌「なぜ環境問題は重要なのか?」
- ⭕「あなたの好きな場所が汚染されたら、どう感じる?」
- ❌「貧困問題についてどう思うか?」
- ⭕「もしあなたが明日から学校に通えなくなったら?」
体験の場を設定する
知識だけでなく、五感を通じた体験を重視します。
- ゲストスピーカーを招いた対話セッション
- 課題の現場を訪問するフィールドトリップ
- ロールプレイやシミュレーションゲーム
- プロトタイプ作成などのものづくり体験
失敗を恐れない環境づくり
社会課題に取り組む際、「正解」はありません。試行錯誤を奨励し、失敗から学ぶ姿勢を育てます。
- 「うまくいかなかったことから何を学んだ?」という問いかけ
- プロセスを重視した評価基準の設定
- 失敗事例の共有と分析の機会
- 「やり直し」や「方向転換」の奨励
Study Valley TimeTactで実現する「自分ごと化」のサポート
生徒が社会課題を自分ごととして捉え、深い探究を行うためには、適切なツールとサポート体制が必要です。Study Valley TimeTactは、この課題解決に特化した機能を提供しています。
興味関心マッピング機能
TimeTactの「興味関心マッピング」機能では、生徒の趣味、特技、関心事をビジュアル化し、それらと社会課題を結びつける支援を行います。
- 生徒の「好き」を起点とした課題発見
- AIによる関連社会課題の提案
- 同じ興味を持つ生徒同士のマッチング
- 個別最適化された探究テーマの推奨
リアルな事例データベース
全国の高校生が取り組んだ身近な社会課題の探究事例を豊富に収録。
- 地域別・テーマ別に検索可能な事例集
- 成功事例だけでなく、失敗から学んだ事例も収録
- 取り組みのプロセスが詳細に記録された探究ストーリー
- 先輩たちからのアドバイスやヒント
フィールドワーク支援ツール
現場での学びを効果的に記録・整理する機能群。
- インタビュー記録テンプレート
- 観察記録の構造化ツール
- 写真・動画と気づきを紐づける機能
- フィールドノートの自動整理・分析
協働探究プラットフォーム
社会課題は一人では解決できません。仲間と協働する環境を提供します。
- 校内・校外の仲間とつながる探究コミュニティ
- 専門家や実践者からのフィードバック機能
- アイデアの共有とブラッシュアップの場
- 協働プロジェクトの進捗管理ツール
まとめ:社会課題を「自分ごと」にする探究へ
「とりあえずSDGs」から脱却し、生徒が社会課題を自分ごととして捉えるには、身近な問題から出発し、体験を通じて当事者意識を育てることが重要です。教員は、生徒の興味関心と社会課題をつなぐファシリテーターとして、適切な問いかけと体験の場を提供する必要があります。
Study Valley TimeTactは、このプロセスを強力にサポートし、生徒一人ひとりが情熱を持って取り組める探究活動の実現を支援します。社会課題の解決は、まず「自分ごと」として捉えることから始まります。その第一歩を、今日から踏み出してみませんか。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。