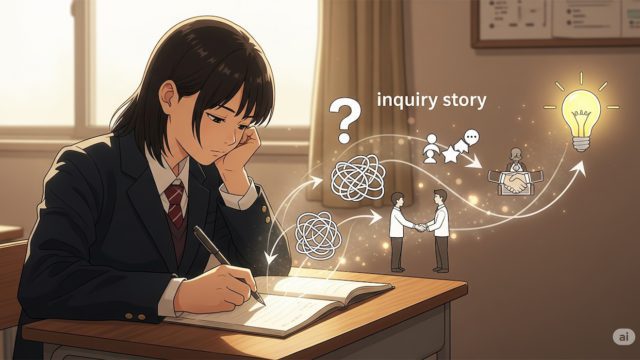探究の「成果物」と「プロセス記録」、大学はどちらを重視すべきか?
総合型選抜や学校推薦型選抜において、高校生の探究活動をどう評価するかは、大学入試担当者にとって重要な課題です。特に悩ましいのが、完成された「成果物」と、そこに至るまでの「プロセス記録」のどちらを重視すべきかという問題です。本記事では、両者の価値を詳しく分析し、真に優秀な学生を見抜くための評価方法について、実践的な観点から解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
探究活動の評価で直面する二つのジレンマ
多くの大学入試担当者は、探究活動の評価において以下のようなジレンマに直面しています。見栄えの良い成果物を提出した生徒が、必ずしも深い探究を行っていたとは限らない一方で、プロセス記録が充実していても、具体的な成果に結びついていないケースもあります。
成果物重視の評価がもたらす問題点
成果物だけを重視した評価には、いくつかの重大な問題があります。
- 外部支援の影響を見抜けない:塾や保護者の過度な支援により作られた成果物
- 表面的な完成度に惑わされる:デザインや体裁は整っているが、内容が浅い作品
- 失敗から学ぶ経験を評価できない:試行錯誤の価値が反映されない
- 協働性や粘り強さが見えない:個人の能力のみが評価対象となりがち
プロセス記録偏重の落とし穴
一方、プロセス記録ばかりを重視することにも課題があります。
- 活動量と質の混同:記録の量が多いだけで、深い思考が伴っていない
- 後付けの美化:実際とは異なる理想的なプロセスを記述する可能性
- 実行力の軽視:計画や思考は優れているが、実現できていない
- 客観的評価の困難さ:主観的な記述が多く、評価基準の統一が難しい
成果物とプロセス記録、それぞれが示す生徒の能力
成果物とプロセス記録は、それぞれ異なる側面から生徒の能力を示しています。大学として求める人材像に応じて、両者のバランスを適切に設定することが重要です。
成果物から読み取れる能力
質の高い成果物からは、以下のような能力を評価することができます。
- 実行力と完遂能力:アイデアを形にする力
- 創造性と独自性:新しい視点や解決策の提示
- 技術的スキル:必要な知識やツールの習得と活用
- 社会的インパクト:他者への影響力や貢献度
プロセス記録が明らかにする資質
充実したプロセス記録からは、次のような資質を見出すことができます。
- 思考の深さと論理性:課題設定から解決に至る思考過程
- 学習能力と成長性:失敗から学び、改善する姿勢
- メタ認知能力:自己の活動を客観的に振り返る力
- 協働性とコミュニケーション力:他者との関わりや役割分担
理想的な評価方法:統合的アプローチの提案
成果物とプロセス記録の二項対立ではなく、両者を有機的に結びつけた統合的な評価方法を構築することが、真に優秀な学生を見抜く鍵となります。
1. 成果物とプロセスの一貫性を評価する
最も重要なのは、プロセス記録に記された思考や活動が、成果物にどのように反映されているかを確認することです。
- 課題設定の経緯が成果物の目的と合致しているか
- 試行錯誤の痕跡が最終成果に活かされているか
- 協働の記録と成果物の多面性が対応しているか
2. 段階的評価システムの導入
探究活動の各段階で異なる評価基準を設定し、総合的に判断します。
- 課題設定段階:問いの質と社会的意義(プロセス重視)
- 調査・実験段階:方法論の妥当性と実行力(バランス型)
- 分析・考察段階:論理的思考と批判的思考(プロセス重視)
- 成果発表段階:表現力と影響力(成果物重視)
3. 面接での検証プロセス
書類審査だけでなく、面接で成果物とプロセス記録の整合性を確認することが重要です。
- 「なぜこのテーマを選んだのか」(動機の確認)
- 「最も苦労した点は何か」(プロセスの深掘り)
- 「もう一度やるなら何を変えるか」(メタ認知の確認)
- 「この経験から何を学んだか」(学習成果の言語化)
4. ルーブリックの活用と改善
成果物とプロセスの両方を含む包括的なルーブリックを作成し、継続的に改善します。
- 各評価項目の配点を学部・学科の特性に応じて調整
- 具体的な評価基準と例示の提供
- 複数評価者による検証とフィードバック
Study Valley TimeTactで実現する包括的な探究評価
大学が理想的な探究評価を実現するためには、高校での探究活動の全体像を把握できるシステムが必要です。Study Valley TimeTactは、成果物とプロセス記録の両方を効果的に管理・評価できるプラットフォームとして、多くの教育機関から支持されています。
TimeTactが提供する評価支援機能
TimeTactは、大学の入試担当者が求める包括的な評価を可能にします。
- デジタルポートフォリオ機能:成果物とプロセス記録を時系列で一元管理
- 活動ログの自動記録:生徒の探究活動を客観的に追跡
- ルーブリック作成ツール:大学独自の評価基準を簡単に設定
- 評価の可視化:成果とプロセスのバランスを視覚的に把握
高校との連携による質の高い情報収集
TimeTactを通じて、高校での探究活動の実態を正確に把握できます。
- 指導教員からのコメントや評価の確認
- グループ活動での個人の貢献度の把握
- 外部連携先からのフィードバック閲覧
- 活動の継続性と発展性の追跡
まとめ:本質を見抜く評価へのパラダイムシフト
探究活動の評価において、「成果物」と「プロセス記録」のどちらかを選ぶのではなく、両者を統合的に評価することで、生徒の真の能力と可能性を見抜くことができます。重要なのは、華やかな成果物の背後にある思考の深さと、地道なプロセスが生み出す確かな成果の両方を評価することです。
大学入試における探究評価は、単なる選抜手段ではありません。未来の社会で活躍する人材を見出し、その成長を支援する第一歩です。成果物とプロセス記録の適切なバランスを保ちながら、一人ひとりの生徒が持つ可能性を丁寧に評価することで、大学教育の新たな価値を創造していくことができるでしょう。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。