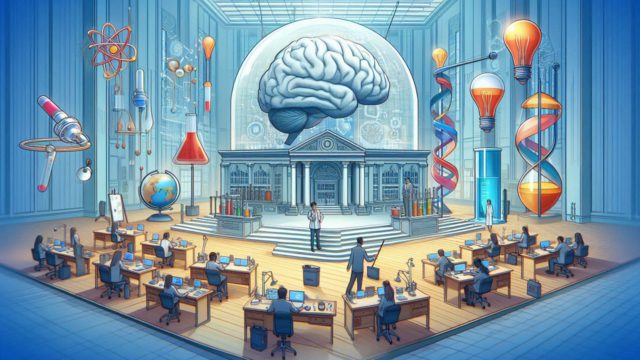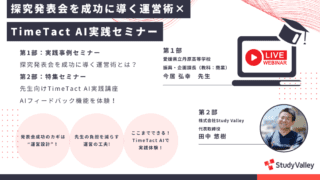出張講義の効果を最大化する秘訣。一度きりのイベントで終わらせない高校との関係構築術
大学の出張講義は、高校生に学問の魅力を伝える貴重な機会です。しかし、多くの大学では「年に1回訪問して90分話して終わり」という一過性のイベントに留まっているのが現実です。本記事では、出張講義を起点として高校との継続的な関係を構築し、学生募集や高大連携の成果を最大化する具体的な方法について、成功事例とともに解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
なぜ多くの出張講義が「一度きり」で終わってしまうのか
全国の大学を対象にした調査によると、出張講義を実施している大学の約80%が「効果が限定的」「継続性に課題がある」と回答しています。その背景には、構造的な問題が存在しています。
出張講義が抱える5つの課題
現状の出張講義には、以下のような課題が指摘されています:
- 事前準備の不足:高校側のニーズや生徒の実態を把握せずに実施
- 一方通行の内容:大学教員が専門分野を語るだけで、生徒との対話が少ない
- フォローアップの欠如:講義後の質問対応や追加情報提供がない
- 担当者間の連携不足:教員個人に依存し、組織的な関係構築ができていない
- 効果測定の未実施:講義の成果を検証せず、改善につながらない
高校教員から見た出張講義の実態
高校の進路指導担当教員への聞き取り調査では、以下のような率直な意見が寄せられています:
- 「大学の先生の話は難しすぎて、生徒がついていけないことが多い」(公立高校・進路指導主任)
- 「せっかく来ていただいても、その後の接点がなく関係が続かない」(私立高校・3年担任)
- 「複数の大学から似たような内容の講義依頼があり、差別化が図れない」(公立高校・教務主任)
- 「生徒の探究活動と連動させたいが、単発では難しい」(私立高校・探究担当)
生徒の本音:出張講義への評価
出張講義を受けた高校生1,500人へのアンケート結果も、課題を浮き彫りにしています:
- 「とても興味深かった」:28%
- 「まあまあ興味深かった」:41%
- 「あまり興味が持てなかった」:23%
- 「全く興味が持てなかった」:8%
さらに重要なのは、「その大学に進学したくなったか」という質問に対して、「強くそう思う」と答えた生徒はわずか12%に留まっている点です。
効果的な出張講義の3つの成功要因
一方で、出張講義を起点に高校との強固な関係を築き、志願者増加につなげている大学も存在します。成功事例の分析から、3つの重要な要因が明らかになりました。
成功要因1:徹底した事前準備とカスタマイズ
効果的な出張講義は、準備段階から始まっています。高校の特性や生徒のニーズに合わせたカスタマイズが不可欠です。
成功事例:A大学工学部の「オーダーメイド型出張講義」
- 事前調査:訪問2ヶ月前から高校教員と複数回の打ち合わせ
- ニーズ把握:生徒の学力レベル、興味関心、進路希望を詳細に調査
- 内容調整:高校の探究テーマに合わせて講義内容をカスタマイズ
- 教材準備:生徒が実際に手を動かせる実験キットを持参
- 成果:参加生徒の満足度95%、翌年の志願者が前年比40%増加
成功要因2:双方向性とアクティブラーニング
一方的な講義ではなく、生徒が主体的に参加できる仕組みの導入が重要です。
効果的な双方向型プログラムの要素
- アイスブレイク:最初の10分で生徒の緊張をほぐす工夫
- グループワーク:4-5人のグループで課題に取り組む時間を設定
- プレゼンテーション:生徒が考えたアイデアを発表する機会
- 質疑応答:講義時間の30%以上を対話に充てる
- フィードバック:生徒の発言や質問に対する丁寧な応答
成功要因3:継続的なフォローアップ体制
出張講義後の継続的な関わりが、真の関係構築につながります。
成功事例:B大学の「年間サポートプログラム」
- 即日フォロー:講義当日に参加生徒全員にサンクスメール送信
- 1週間後:質問受付期間を設定し、オンラインで追加説明
- 1ヶ月後:関連する学習資料や大学情報を提供
- 3ヶ月後:探究活動の進捗確認と助言
- 6ヶ月後:オープンキャンパスへの特別招待
- 1年後:進路決定状況の確認と個別相談対応
出張講義を起点とした関係構築の5ステップ
ここからは、出張講義を一過性のイベントで終わらせず、継続的な高大連携へと発展させる具体的なステップを解説します。
ステップ1:戦略的なターゲティング(実施3ヶ月前)
すべての高校に同じアプローチをするのではなく、戦略的に連携先を選定することが重要です。
ターゲット校選定の基準
- 進学実績:過去の志願者・入学者データから親和性の高い高校を特定
- 地理的要因:アクセスしやすく、継続的な関係構築が可能な立地
- 教育方針:大学の理念と共通する教育目標を持つ高校
- 探究活動:活発な探究学習を展開し、高大連携に積極的な姿勢
初期アプローチの方法
- 校長・教頭への挨拶:組織的な関係構築の意思を明確に伝える
- 進路指導部との面談:高校のニーズと課題を詳細にヒアリング
- 年間計画の提案:単発ではなく年間を通じた連携プログラムを提示
- win-winの関係設計:大学・高校双方にメリットがある内容を協議
ステップ2:綿密な事前準備(実施1-2ヶ月前)
講義の成功は準備の質で決まると言っても過言ではありません。
必須の準備項目チェックリスト
- ☐ 参加生徒の学年・人数・学力レベルの確認
- ☐ 生徒の興味関心分野の事前アンケート実施
- ☐ 高校の年間指導計画との連動性確認
- ☐ 使用可能な設備・機材の確認
- ☐ 講義内容の高校教員によるレビュー
- ☐ 配布資料・教材の準備
- ☐ アクティビティ用具の準備
- ☐ 事後フォローの計画策定
ステップ3:インパクトのある講義実施(当日)
限られた時間で最大の効果を生み出すための講義設計が重要です。
90分講義の理想的な時間配分
- 導入(10分)
- アイスブレイク:身近な話題から専門分野へ
- 本日の目標提示:生徒が得られる学びを明確に
- 講義パート1(20分)
- 基礎知識の解説:専門用語を避け、平易な言葉で
- 具体例の提示:生徒の日常と関連付ける
- アクティビティ(25分)
- グループワーク:4-5人で課題に取り組む
- 実験・実習:手を動かして理解を深める
- 発表・共有(15分)
- グループ発表:各グループ2-3分で成果を共有
- 講師からのフィードバック:良い点を具体的に褒める
- 講義パート2(15分)
- 発展的内容:大学での学びにつなげる
- 最新研究紹介:ワクワクする未来を見せる
- まとめ・Q&A(5分)
- 本日の振り返り:重要ポイントの確認
- 次のステップ:継続的な学びへの誘導
ステップ4:即効性のあるフォローアップ(実施後1週間)
講義直後の「熱い」うちに次の行動を促すことが重要です。
フォローアップのタイムライン
- 当日中
- 参加生徒へのサンクスメール配信
- 追加資料のダウンロードリンク提供
- アンケートフォームの送信
- 3日以内
- 生徒からの質問への回答
- 高校教員への実施報告書送付
- 写真・動画などの記録共有
- 1週間以内
- アンケート結果の分析と共有
- 次回プログラムの提案
- 関連イベントの案内
ステップ5:長期的な関係構築(実施後1ヶ月〜)
出張講義を起点に、多層的な連携プログラムへと発展させます。
継続的な連携メニューの例
- 探究活動支援
- テーマ設定の助言
- 研究手法の指導
- 大学施設の利用提供
- 教員研修
- 高校教員向けセミナー開催
- 最新の学問動向の共有
- 指導方法の情報交換
- 生徒の継続学習
- オンライン講座の提供
- 大学の授業聴講機会
- 研究室訪問プログラム
- 共同プロジェクト
- 地域課題解決PBL
- 高大連携研究発表会
- 国際交流プログラム
成功事例に学ぶ:3大学の革新的アプローチ
実際に出張講義を起点として高校との強固な関係を築いた3つの大学の事例を詳しく見ていきましょう。
事例1:C大学理学部「サイエンス・パートナーシップ・プログラム」
プログラムの特徴
- 3年間の包括連携:高校1年から3年まで段階的にプログラムを提供
- 教員チーム制:複数の教員が役割分担して継続的に関与
- 生徒の成長記録:ポートフォリオで3年間の成長を可視化
実施内容
- 1年次:基礎科学への興味喚起(年3回の出張講義)
- 2年次:探究活動の指導(月1回のオンラインメンタリング)
- 3年次:進路選択支援(研究室訪問、模擬講義)
成果
- 連携高校からの志願者:3年間で250%増加
- 入学後の成績:連携校出身者のGPAが平均0.3ポイント高い
- 高校の評価:「生徒の理系進学意欲が飛躍的に向上」
事例2:D大学経営学部「ビジネス・イノベーション・ラボ」
プログラムの特徴
- 実践型プロジェクト:地元企業と連携した課題解決型学習
- 大学生メンター:学部生が高校生の活動をサポート
- 成果の社会実装:優秀なアイデアは実際に企業が採用
プロセス
- キックオフ講義:起業家精神とイノベーションの基礎
- チーム形成:高校生5人+大学生1人のチーム編成
- 企業訪問:課題提供企業での現場体験
- アイデア開発:3ヶ月間のプロジェクト活動
- 最終発表会:企業経営者、大学教員による審査
インパクト
- 参加生徒の78%が経営学部に興味を持つ
- プログラム修了生の35%が実際に同大学へ進学
- 地域企業との関係強化により、インターンシップ先が40%増加
事例3:E大学教育学部「未来の教師育成プロジェクト」
独自の工夫
- 教職志望者への特化:教師を目指す高校生に焦点
- 実習型プログラム:大学の模擬授業施設を活用
- 現職教員との交流:卒業生教員によるメンタリング
年間スケジュール
- 4-5月:教職の魅力を伝える出張講義
- 6-7月:大学での模擬授業体験(2日間)
- 8月:サマースクールでの指導体験
- 9-11月:教育実習見学
- 12-3月:進路相談・入試対策支援
効果
- 教職志望の明確化:参加者の92%が志望を強化
- 早期離職の減少:プログラム経験者の教員定着率が15%向上
- 地域教育への貢献:優秀な教員の地元定着に寄与
Study Valley TimeTactで実現する次世代の高大連携
ここまで見てきたように、効果的な高大連携には継続性と組織的な取り組みが不可欠です。しかし、「人的リソースが限られている」「ノウハウがない」という課題を抱える大学も多いでしょう。そこで活用したいのが、デジタルプラットフォームによる効率化です。
TimeTactが解決する出張講義の課題
Study Valley TimeTactは、出張講義を起点とした高大連携を包括的にサポートするプラットフォームです:
1. 事前準備の効率化
- 高校情報データベース:各校の特性や過去の連携実績を一元管理
- ニーズマッチング:高校の要望と大学の提供内容を自動マッチング
- スケジュール調整:講師と高校の日程調整を簡単に
- 教材共有:過去の成功事例や教材をライブラリ化
2. 継続的な関係構築支援
- コミュニケーション履歴:高校とのやり取りを時系列で記録
- フォローアップ自動化:適切なタイミングでリマインド
- 生徒の成長記録:出張講義から入学後まで一貫して追跡
- 効果測定ダッシュボード:KPIを可視化し、改善点を明確化
3. 探究活動との連動
- 探究テーマ提供:大学の研究分野に基づくテーマ提案
- オンラインメンタリング:継続的な指導を効率的に実施
- 成果共有プラットフォーム:高校生の探究成果を大学教員が評価
- 高大接続の実質化:探究活動の大学での継続を支援
TimeTact活用による成果事例
プラットフォームを活用している大学では、以下のような成果が報告されています:
- F大学:出張講義の準備時間が50%削減、実施校数が2倍に増加
- G大学:高校との継続率が85%に向上(導入前は30%)
- H大学:連携高校からの志願者が平均60%増加
まとめ:出張講義を「点」から「線」へ、そして「面」へ
出張講義は、高大連携の入口に過ぎません。真の価値は、その後の継続的な関係構築にあります。一過性のイベントで終わらせず、戦略的なターゲティング、綿密な準備、インパクトのある実施、即効性のあるフォローアップ、そして長期的な関係構築へとつなげることが重要です。
成功している大学の事例が示すように、出張講義を起点とした包括的な連携プログラムは、志願者増加だけでなく、入学後の学生の質向上、地域貢献、大学のブランド力向上など、多面的な効果をもたらします。
そして、Study Valley TimeTactのようなプラットフォームを活用することで、限られたリソースでも効果的な高大連携を実現できます。デジタルツールによる効率化と、人と人との温かい交流を組み合わせることで、新しい高大連携の形が生まれるのです。
出張講義を「点」の活動から「線」の関係へ、そして多様なプログラムが織りなす「面」の連携へと発展させる。それが、これからの大学に求められる高校との関係構築の姿ではないでしょうか。一度きりで終わらない、継続的で実りある高大連携を、今こそ始めてみませんか。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。