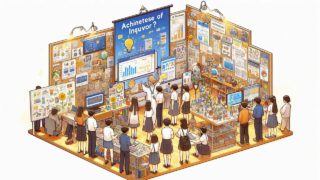高校の先生は、大学の「何」を知りたいのか?訪問時に必ず伝えるべき3つの情報
高校訪問は大学の学生募集において重要な活動ですが、多くの大学関係者が「何を話せば良いか分からない」「パンフレットを渡すだけで終わってしまう」という悩みを抱えています。実は、高校の先生が本当に知りたい情報と、大学側が伝えたい情報には大きなギャップが存在しています。本記事では、高校教員へのヒアリング調査を基に、高校訪問で必ず伝えるべき3つの情報と、効果的な伝え方について解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
高校訪問の現状:なぜコミュニケーションがすれ違うのか
まずは、高校訪問における典型的な課題を整理し、なぜ効果的なコミュニケーションが取れていないのかを明らかにします。
大学側の「伝えたい」と高校側の「知りたい」のミスマッチ
多くの大学が高校訪問で伝えている情報は以下のようなものです:
- 大学の歴史や規模
- 学部・学科の紹介
- 入試制度の概要
- 就職率や資格取得実績
- キャンパスの設備
一方、高校の先生が本当に知りたいのは:
- 自分の生徒に合っているか(生徒との適合性)
- 入学後どのように成長できるか(教育の質と成果)
- どんなサポートがあるか(学生支援体制)
- 探究活動がどう評価されるか(入試での評価観点)
- 他大学との違いは何か(独自性・強み)
このギャップが、「訪問しても手応えがない」「時間の無駄に感じる」という両者の不満につながっています。
高校教員の本音:アンケート調査から見えてきたこと
全国の高校教員300名を対象に実施したアンケート調査では、以下のような声が寄せられました:
【大学訪問への不満】
- 「パンフレットに書いてあることしか話さない」(進路指導主任・公立高校)
- 「うちの生徒の学力レベルを理解せずに話をされる」(3年担任・私立高校)
- 「探究活動について質問しても曖昧な回答しか返ってこない」(探究担当・公立高校)
- 「毎年同じ説明で、新しい情報がない」(進路指導部長・公立高校)
【本当に知りたいこと】
- 「具体的にどんな生徒が向いているのか」(2年担任・私立高校)
- 「入学後につまずく生徒の特徴と対策」(進路指導主任・公立高校)
- 「探究活動の評価方法と重視するポイント」(探究主任・公立高校)
- 「他大学にはない独自の教育プログラム」(進路指導部・私立高校)
必ず伝えるべき情報その1:生徒の「適合性」に関する具体的情報
高校の先生が最も知りたいのは、「どんな生徒がその大学に向いているか」という適合性に関する情報です。
学力だけでない多面的な適合性を伝える
従来の「偏差値○○以上」という単純な基準ではなく、以下のような多面的な観点から適合性を説明することが重要です:
【学習スタイルの適合性】
- 理論重視型 vs 実践重視型:講義中心か、実習・フィールドワークが多いか
- 個人学習型 vs グループ学習型:ゼミやプロジェクトでの協働学習の比重
- 専門特化型 vs 学際融合型:早期から専門を深めるか、幅広く学ぶか
【具体的な伝え方の例】
「本学の経済学部では、1年次から少人数ゼミでディスカッションを重視しています。自分の意見を積極的に発信したい生徒、仲間と議論しながら学びたい生徒に特に向いています。一方、じっくり一人で考えることを好む生徒には、個別研究の時間も確保していますので、両方のタイプに対応できます。」
入学後の成長イメージを具体的に描く
抽象的な説明ではなく、具体的な学生の成長ストーリーを示すことで、先生方は生徒の将来像をイメージしやすくなります:
【成長事例の提示方法】
- 入学時の状態:「人前で話すのが苦手だった学生A君」
- 大学での経験:「プレゼンテーション授業、留学プログラム参加」
- 成長の過程:「失敗を重ねながら徐々に自信をつけていった」
- 現在の姿:「学会発表で優秀賞、大手企業の営業職に内定」
ミスマッチを防ぐための正直な情報開示
良い面ばかりでなく、向いていない生徒の特徴も正直に伝えることで、信頼関係が構築できます:
- 「課題が多いので、部活動との両立は相当な覚悟が必要です」
- 「英語の授業が多いため、英語に苦手意識がある生徒は入学後苦労する可能性があります」
- 「都心から離れているので、通学時間を有効活用できる生徒が向いています」
必ず伝えるべき情報その2:探究活動の評価方法と活用実態
新学習指導要領の実施により、高校では探究活動が必修化されました。先生方は「生徒の探究活動が大学でどう評価されるか」を切実に知りたがっています。
探究活動の評価における3つの視点
大学が探究活動をどのような視点で評価しているかを、具体的に説明します:
1. プロセス重視の評価
- 課題設定力:なぜそのテーマを選んだか、問題意識の深さ
- 情報収集・分析力:どのような方法で調査したか、データの扱い方
- 論理的思考力:仮説から結論に至る道筋の妥当性
2. 成長と学びの評価
- 振り返りの質:失敗から何を学んだか
- 改善への取り組み:PDCAサイクルを回せているか
- メタ認知能力:自己の学びを客観視できているか
3. 大学での学びとの接続性
- 志望分野との関連:探究テーマと志望学部の関係性
- 発展可能性:大学でさらに深めたい問いがあるか
- 学問的興味:知的好奇心の広がりと深さ
評価の具体例を用いた説明
実際の評価例を示すことで、先生方の理解が深まります:
【高評価の例】
「地域の高齢者の買い物難民問題に取り組んだ生徒がいました。単に調査するだけでなく、実際に移動販売業者と交渉し、試験的な販売会を実現させました。結果は失敗でしたが、その原因を分析し、改善案を提示していました。このような実践と省察のサイクルを評価しています。」
【評価のポイント】
「テーマの独自性や成果の大きさよりも、生徒がどれだけ主体的に取り組み、何を学んだかを重視しています。ありふれたテーマでも、深い考察があれば高く評価します。」
入学後の探究活動支援体制
高校での探究活動が大学でどう発展するかも重要な情報です:
- 初年次ゼミでの継続研究:高校での探究を深める機会
- 学部横断プロジェクト:異分野との融合による新たな視点
- 研究資金支援:学生の自主研究への予算配分
- 学会発表機会:研究成果を外部で発表する支援
必ず伝えるべき情報その3:卒業生の「リアルな進路」と成長の軌跡
就職率や就職先企業名だけでなく、卒業生がどのような過程を経て進路を決定し、社会でどう活躍しているかという情報が求められています。
数字では表せない卒業生の成長ストーリー
単なる就職実績の羅列ではなく、具体的な卒業生の事例を通じて、大学教育の成果を伝えます:
【事例1:進路変更を経験した学生】
「教員志望で入学したB さんは、教育実習で挫折を経験しました。しかし、キャリアセンターの個別相談を通じて、教育への情熱を企業の人材育成に活かす道を発見。現在は大手企業の研修部門で、新入社員教育を担当しています。」
【事例2:探究活動を仕事につなげた学生】
「高校時代に地域活性化をテーマに探究していたC君は、大学でさらに研究を深め、地域おこし協力隊として就職。在学中に培ったネットワークを活かし、現在は起業準備中です。」
多様な進路選択を支える支援体制
画一的なキャリア支援ではなく、個々の学生に合わせた多様な支援があることを伝えます:
【キャリア支援の具体例】
- 1年次からのキャリア探索:自己分析ワークショップ、業界研究セミナー
- インターンシップの充実:長期・短期、国内・海外の多様なプログラム
- 個別メンタリング制度:教員や卒業生による継続的な相談支援
- 起業支援プログラム:ビジネスプランコンテスト、起業家育成講座
卒業後のフォローアップ体制
卒業して終わりではなく、継続的な関係性があることも重要な情報です:
- 卒業生ネットワーク:業界別・地域別の交流会
- リカレント教育:卒業生向けの学び直しプログラム
- 転職・キャリアチェンジ支援:卒業後も利用可能な相談窓口
- 在学生へのメンター:卒業生が後輩を支援する仕組み
効果的な高校訪問のための実践的アドバイス
3つの情報を効果的に伝えるための、具体的な訪問準備と実施方法を解説します。
訪問前の準備:相手校を知る
効果的な訪問のためには、訪問先の高校について事前に理解を深めることが不可欠です:
- 高校のWebサイトチェック:教育方針、探究活動の取り組み、進路実績
- 過去の進学実績確認:自大学への進学者の動向、競合大学の状況
- 地域特性の把握:通学圏、地域の産業構造、教育熱
- 担当者との事前連絡:訪問の目的、話したい内容の共有
訪問時の工夫:双方向のコミュニケーション
一方的な説明ではなく、対話を通じて相手のニーズを引き出すことが重要です:
【効果的な質問例】
- 「貴校の生徒さんの特徴や強みを教えていただけますか?」
- 「探究活動で生徒さんが困っていることはありますか?」
- 「進路指導で課題に感じていることはありますか?」
- 「本学に期待することは何でしょうか?」
【持参すべき資料】
- 具体的な学生事例集(写真付き)
- 探究活動評価のルーブリック
- 卒業生の進路マップ(学部別・業界別)
- 高校との連携プログラム一覧
訪問後のフォローアップ:関係性の継続
訪問は一度きりではなく、継続的な関係構築の第一歩と捉えます:
- 訪問後の御礼と報告:話した内容のサマリー送付
- 追加情報の提供:質問への回答、関連資料の送付
- 定期的な情報発信:入試情報、イベント案内、学生の活躍
- 次回訪問の提案:季節ごとの定期訪問、特別企画の案内
Study Valley TimeTactで実現する高大連携の見える化
高校訪問で得た情報や関係性を一過性のものにしないためには、組織的な情報管理が必要です。
TimeTactが提供する高大連携支援機能
Study Valley TimeTactは、高大連携を効果的に進めるための以下の機能を提供します:
- 高校情報データベース:訪問履歴、担当者情報、生徒の特徴を一元管理
- 探究活動マッチング:高校の探究テーマと大学の研究分野をマッチング
- 連携プログラム管理:出張講義、大学見学、探究支援の実施状況を可視化
- 効果測定ツール:連携活動の成果(志願者数、入学者数)を分析
データに基づく戦略的な高校訪問
TimeTactを活用することで、以下のような戦略的アプローチが可能になります:
- 優先訪問校の選定:過去の実績データから効果的な訪問先を特定
- 最適な訪問時期の把握:高校の年間スケジュールに合わせた計画立案
- 担当者別の訪問成果分析:効果的な訪問手法の共有と改善
- 長期的な関係性の可視化:継続的な連携による成果の追跡
まとめ:真の高大連携に向けて
高校訪問で必ず伝えるべき3つの情報をまとめると:
- 生徒の適合性に関する具体的情報:どんな生徒が向いているか、成長できるか
- 探究活動の評価方法と活用実態:何を重視し、どう支援するか
- 卒業生のリアルな進路と成長の軌跡:数字では見えない成長ストーリー
これらの情報を効果的に伝えることで、高校の先生との信頼関係が構築され、真の意味での高大連携が実現します。単なる学生募集活動ではなく、共に次世代を育てるパートナーとしての関係を築くことが、これからの大学に求められています。Study Valley TimeTactは、そのような持続可能な高大連携を支援し、教育の質向上に貢献します。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。