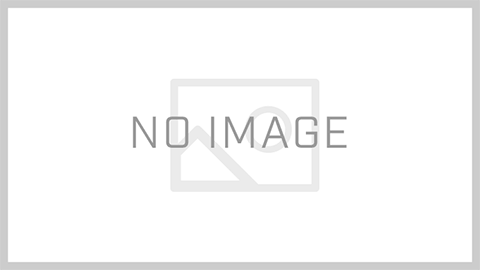志願者増に直結した、高大連携の成功事例。ある大学は、なぜ高校生の心を掴んだのか
少子化が進む中、多くの大学が学生募集に苦戦しています。しかし、そんな逆風の中でも、高大連携を戦略的に活用することで志願者を大幅に増やした大学があります。本記事では、実際に志願者数を3年間で1.5倍に増やしたA大学の事例を中心に、効果的な高大連携の具体的な手法と、高校生の心を掴むポイントについて詳しく分析します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
A大学が直面していた危機的状況
地方都市にあるA大学(学生数約3,000人)は、2019年頃まで深刻な定員割れに悩んでいました。18歳人口の減少に加え、都市部の大学への流出が続き、志願倍率は1.2倍まで低下。このままでは大学の存続自体が危ぶまれる状況でした。
従来の募集活動の限界
A大学も他の多くの大学と同様、以下のような従来型の募集活動を行っていました:
- 年数回のオープンキャンパス
- 高校訪問による進路指導室への説明
- 大学案内パンフレットの配布
- 進学相談会への参加
しかし、これらの活動は他大学との差別化が困難で、高校生に強い印象を残すことができませんでした。特に、探究学習に熱心に取り組む意欲的な高校生たちには、従来の一方的な情報提供では響かなかったのです。
転機となった「探究パートナーシップ・プログラム」の導入
2020年、A大学は発想を転換し、「探究パートナーシップ・プログラム」という独自の高大連携プログラムを立ち上げました。これは、単なる出張講義や大学見学ではなく、高校の探究学習と大学の教育・研究を有機的に結びつける画期的な取り組みでした。
プログラムの3つの柱
1. 探究メンター制度
大学の教員と大学院生が、高校生の探究活動に対して継続的にメンタリングを行う制度です。単発の指導ではなく、1年間を通じて同じメンターが伴走支援することで、深い信頼関係を構築しました。
2. 大学リソースの全面開放
図書館、実験施設、研究室など、大学の施設を高校生に開放。特に、大学図書館の専門書や学術データベースへのアクセスを可能にしたことで、高校生の探究の質が飛躍的に向上しました。
3. 合同研究発表会の開催
高校生と大学生が同じステージで研究発表を行う合同発表会を年2回開催。高校生にとっては大学レベルの研究に触れる機会となり、大学生にとっては初心に帰る良い刺激となりました。
高校生の心を掴んだ5つの成功要因
なぜA大学のプログラムは高校生の心を掴むことができたのでしょうか。その成功要因を分析すると、以下の5つのポイントが浮かび上がります。
1. 「教える」から「共に探究する」への転換
従来の高大連携では、大学が高校に「教える」という上下関係が前提でした。しかし、A大学は高校生を「共に学ぶパートナー」として位置づけました。
例えば、環境問題をテーマにした探究では、高校生の「なぜプラスチックごみは減らないのか」という素朴な問いから出発し、大学の研究者も一緒になって新たな視点を探りました。この姿勢が、高校生に「大学は自分たちを尊重してくれる場所」という印象を与えたのです。
2. 個別最適化されたサポート
画一的なプログラムではなく、生徒一人ひとりの興味関心に応じたオーダーメイドのサポートを提供しました。
実施例:
- 医療に興味がある生徒→医学部の研究室見学と臨床医との対話
- AIに関心がある生徒→情報工学科でのプログラミング体験
- 地域活性化がテーマの生徒→経済学部教員との共同フィールドワーク
3. 大学生との自然な交流機会
メンターとして関わる大学院生だけでなく、学部生もサポーターとして積極的に参加。年齢の近い先輩との交流は、高校生にとって大学生活をリアルにイメージする機会となりました。
特に効果的だったのは、探究活動の休憩時間に設けた「フリートーク・カフェ」。お茶を飲みながら、勉強のこと、サークル活動のこと、アルバイトのことなど、ざっくばらんな話ができる雰囲気を作り出しました。
4. 成果の可視化と承認
高校生の探究成果を大学の正式な刊行物に掲載したり、優秀な研究には「学長賞」を授与したりすることで、高校生の努力を形に残しました。
さらに、総合型選抜において、このプログラムでの活動を正式な評価対象とすることを明確にしました。これにより、高校生は安心して探究活動に打ち込むことができました。
5. 保護者・高校教員への丁寧な説明
高校生本人だけでなく、保護者や高校教員への情報提供も重視しました。
実施内容:
- 保護者向け説明会の開催(年3回)
- 高校教員との定期的な情報交換会
- 活動レポートの定期発行
- 保護者も参加できる成果発表会
数字で見る驚きの成果
「探究パートナーシップ・プログラム」導入から3年間で、A大学には以下のような変化が現れました。
志願者数の劇的な増加
- 2019年度:1,200名 → 2022年度:1,800名(1.5倍)
- 特に連携高校からの志願者は2.3倍に増加
- 総合型選抜の志願者は3倍に増加
入学者の質の向上
- 入学後のGPAが平均0.3ポイント上昇
- 1年次の退学率が3.2%から1.8%に減少
- 大学院進学率が15%から22%に上昇
高校との関係性の変化
- 連携高校数:5校→18校
- 年間の高校生参加者数:50名→320名
- リピート参加率:85%(翌年も継続参加)
他大学でも応用可能な成功のエッセンス
A大学の事例から、他大学でも応用可能な成功のポイントを整理します。
1. トップのコミットメント
A大学では学長自らがプログラムの陣頭指揮を執りました。高大連携を一部署の取り組みではなく、大学全体の戦略として位置づけることが重要です。
2. 教職員の意識改革
「高校生に教える」のではなく「高校生と共に学ぶ」というマインドセットの転換が必要です。そのための研修や、成功体験の共有が効果的でした。
3. 継続性の担保
単発のイベントではなく、年間を通じた継続的な関わりが信頼関係構築の鍵となります。そのための予算確保と人員配置が不可欠です。
4. 双方向のメリット設計
高校側のメリットだけでなく、大学側にもメリットがある設計にすることで、持続可能なプログラムとなります。A大学では、高校生との交流が大学教育の改善にもつながりました。
Study Valley TimeTactで実現する効果的な高大連携
A大学のような成功を目指す大学にとって、Study Valley TimeTactは強力な支援ツールとなります。
探究テーマのデータベース化
TimeTactでは、高校生の探究テーマをデータベース化して管理。大学側は自学の強みを活かせるテーマを持つ高校生を効率的に見つけることができます。興味関心のマッチングが、効果的な支援の第一歩となります。
メンタリング履歴の蓄積
メンターによる指導内容や高校生の成長記録をシステム上で一元管理。担当者が変わっても継続的な支援が可能になり、また成功パターンの分析にも活用できます。
成果の可視化とポートフォリオ作成
高校生の探究成果をデジタルポートフォリオとして蓄積。大学の選抜においても、このポートフォリオを評価材料として活用でき、公正で透明性の高い選抜が実現します。
効果測定とPDCAサイクル
プログラムの効果を定量的に測定・分析する機能により、継続的な改善が可能。どの取り組みが志願者増につながったのか、データに基づいた検証ができます。
まとめ:高大連携は大学の未来を変える
A大学の成功事例が示すように、戦略的な高大連携は志願者増に直結するだけでなく、入学者の質の向上、大学教育の活性化など、多面的な効果をもたらします。
成功の鍵は、高校生を「未来の学生候補」としてではなく、「現在の学びのパートナー」として尊重し、共に成長する関係性を築くことです。探究学習を通じた深い関わりは、表面的な大学PRよりもはるかに強い絆を生み出します。
Study Valley TimeTactのようなデジタルツールを活用することで、こうした質の高い高大連携をより効率的に、より多くの高校と実現することが可能になります。少子化の時代だからこそ、一人ひとりの高校生と真摯に向き合い、共に学ぶ姿勢が、大学の持続的な発展につながるのです。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。