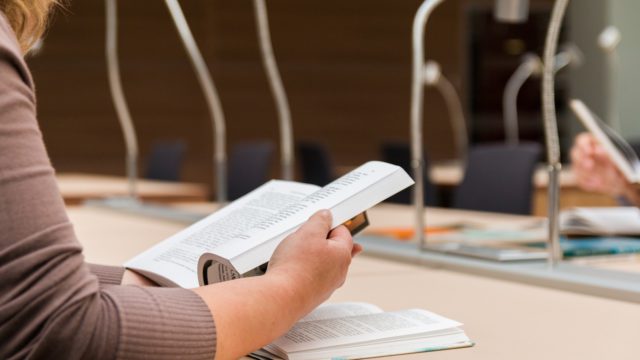あの高校からなぜ志願者が集まる?ターゲット校との戦略的パートナーシップ構築法
「なぜA大学には、毎年うちの高校から多くの生徒が進学するのだろう」――高校の進路指導室でよく聞かれる疑問です。実は、特定の高校から継続的に多くの志願者を獲得している大学には、偶然ではない戦略的な取り組みがあります。本記事では、成功している大学の事例を分析し、ターゲット校との効果的なパートナーシップ構築法を詳しく解説します。

【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
データが物語る「ターゲット校戦略」の驚くべき効果
まず、ターゲット校戦略がいかに効果的であるかを、具体的なデータで見てみましょう。大学入試センターの調査によると、志願者の約70%は「出身高校の先輩が多く進学している大学」を志望校候補に含めています。つまり、特定の高校との強固な関係性は、安定的な志願者確保の基盤となるのです。
成功事例に見る驚異的な数字
事例1:中堅私立B大学の成功
- ターゲット校10校を設定し、5年間で集中的にアプローチ
- 結果:該当校からの志願者が平均320%増加
- 歩留まり率も45%から68%に向上
- 入学後の満足度も一般入学者より15ポイント高い
事例2:地方国立C大学の戦略的展開
- 県内上位校5校と包括連携協定を締結
- 年間を通じた探究学習支援プログラムを実施
- 結果:5年で志願者数が2.8倍に増加
- 地元定着率も62%から81%に改善
なぜ特定の高校から志願者が集まるのか
特定の高校から継続的に志願者が集まる背景には、以下の3つの要因があります。
- 信頼の連鎖効果:先輩が満足して大学生活を送っていることが、後輩への最強の推薦状となる
- 情報の蓄積:高校側に大学の詳細な情報が蓄積され、的確な進路指導が可能になる
- 文化的適合性:高校と大学の教育理念や校風が合致し、スムーズな接続が実現する
ターゲット校を戦略的に選定する5つの視点
効果的なパートナーシップを構築するためには、まず適切なターゲット校を選定することが重要です。成功している大学の選定基準を分析すると、以下の5つの視点が浮かび上がります。
視点1:データに基づく潜在力分析
過去5年間の入試データを分析し、以下の指標でターゲット校を選定します。
- 志願者数の推移:増加傾向にある高校は関心が高まっている証拠
- 合格者の入学率:50%以上なら親和性が高い
- 入学後のGPA:平均以上なら学力的にもマッチしている
- 中退率:低ければ満足度が高い
視点2:地理的・文化的親和性
物理的な距離だけでなく、文化的な距離も重要な選定基準です。
- 通学圏内(片道90分以内)の高校
- 教育理念や校風が類似している高校
- 部活動や課外活動の傾向が合致する高校
- 保護者の大学観が自大学と親和性の高い地域
視点3:探究学習との接続可能性
新しい入試制度を見据え、探究学習に力を入れている高校は重要なターゲットです。
- SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校
- SGH(スーパーグローバルハイスクール)指定校
- 探究学習の先進的な取り組みで知られる高校
- 大学との連携に積極的な姿勢を示している高校
視点4:進路実績と進学志向
高校の進路実績を分析し、自大学とのマッチングを検証します。
- 自大学の競合校への進学実績
- 学部・学科別の進学傾向
- 国公立・私立の志向性
- 浪人率と現役進学率のバランス
視点5:将来性と成長可能性
現在だけでなく、5年後、10年後を見据えた選定も重要です。
- 地域の人口動態と生徒数の推移予測
- 新しい教育プログラムの導入状況
- 進学実績の向上傾向
- 地域での評判と認知度の変化
信頼関係を築く「7つの黄金ルール」
ターゲット校を選定したら、次は具体的な関係構築です。成功している大学が実践している「7つの黄金ルール」を紹介します。
ルール1:継続性を最優先する
単発のイベントではなく、年間を通じた継続的な関わりが信頼関係の基盤となります。
- 年間スケジュールを高校と共同で策定
- 担当者の異動があっても関係性を維持する仕組み
- 最低3年間は同じプログラムを継続実施
ルール2:Give & Giveの精神で接する
最初の2年間は見返りを求めず、高校への貢献に徹することが重要です。
- 進路指導に役立つ情報の無償提供
- 教員研修への講師派遣
- 施設・設備の優先的な開放
- 高校のニーズに応じたカスタマイズ支援
ルール3:現場の教員との関係を重視
管理職だけでなく、実際に生徒と接する教員との関係構築が成功の鍵です。
- 進路指導主任との定期的な情報交換
- 3年生担任団への直接的なアプローチ
- 教科担当教員との専門的な交流
- 若手教員向けの研修機会の提供
ルール4:生徒の成長をともに見守る
入学前から卒業後まで、生徒の成長を高校と共有することで、深い信頼関係が生まれます。
- 入学者の大学での活躍を定期的に報告
- 卒業生の進路や成果を高校にフィードバック
- 在学生による母校訪問の機会を設定
- 成功事例を高校の広報にも活用してもらう
ルール5:探究学習を接点として活用
探究学習は、高大連携の最も効果的な接点となります。
- 大学教員による探究テーマの提案と指導
- 大学の研究施設を活用した探究活動支援
- 大学生メンターによる伴走支援
- 探究発表会への審査員派遣と講評
ルール6:保護者へのアプローチも忘れない
進路選択において、保護者の影響力は依然として大きいため、保護者向けの取り組みも重要です。
- 保護者向け大学説明会の開催
- 教育費や奨学金に関する個別相談会
- 大学の就職支援体制の詳細説明
- 卒業生保護者による体験談の共有
ルール7:データに基づくPDCAサイクル
感覚ではなく、データに基づいて関係性の質を継続的に改善します。
- 各プログラムの参加者数と満足度を測定
- 志願者数・入学者数の変化を追跡
- 高校側のニーズ変化を定期的に調査
- 費用対効果を検証し、最適化を図る
成功事例に学ぶ、具体的な連携プログラムの設計
理論だけでなく、実際に成果を上げている連携プログラムの具体例を見てみましょう。
事例1:年間探究メンタープログラム(D大学)
プログラム概要:
- 4月:大学教員によるキックオフ講演と探究テーマ設定支援
- 5-7月:月2回、大学院生によるオンラインメンタリング
- 8月:大学での夏期集中研究プログラム(3日間)
- 9-11月:研究の深化と論文作成支援
- 12月:大学での探究成果発表会
- 1-3月:優秀者への特別プログラムと入試準備支援
成果:
- 参加者の85%が同大学を受験
- 合格者の入学率92%(一般入試の2倍)
- 入学後の成績も上位25%に集中
事例2:教員協働研究プログラム(E大学)
プログラム概要:
- 高校教員と大学教員が共同研究チームを結成
- 高校の探究授業の教材を共同開発
- 研究成果を学会で共同発表
- 教員の専門性向上と生徒への還元を実現
成果:
- 参加高校教員の満足度98%
- 開発教材を使用した生徒の大学進学意欲が40%向上
- 高校側から継続要請100%
事例3:高大接続入試の共同開発(F大学)
プログラム概要:
- 高校の探究学習と連動した特別入試制度を設計
- 評価基準を高校と共同で策定
- 高校での探究活動を大学の単位として認定
- 入学前教育プログラムも共同実施
成果:
- 新入試での入学者の4年間卒業率95%
- 一般入試入学者より就職内定率が10ポイント高い
- 他の高校からの問い合わせが殺到
Study Valley TimeTactで実現する、次世代の高大連携マネジメント
これらの戦略的パートナーシップを効率的かつ効果的に運営するためには、デジタルツールの活用が不可欠です。Study Valley TimeTactは、高大連携の課題を包括的に解決するプラットフォームとして、多くの大学で導入が進んでいます。
TimeTactが解決する高大連携の3大課題
1. 情報の分断と非効率性
従来、高校との連携情報は担当者個人に依存し、組織的な蓄積ができていませんでした。TimeTactでは、すべての連携活動をデータベース化し、担当者が変わっても継続的な関係維持が可能です。
2. 効果測定の困難さ
「どの連携活動が志願者増に繋がったか」を正確に把握することは困難でした。TimeTactは、各プログラムの参加者を追跡し、最終的な出願・入学までをトラッキング。ROIを明確に算出できます。
3. 個別最適化の限界
高校ごとに異なるニーズに対応することは、人力では限界があります。TimeTactのAI機能は、各高校の特性を分析し、最適な連携プログラムを自動提案。パーソナライズされた関係構築を実現します。
導入大学の成果実績
- G大学:ターゲット校管理の効率化により、連携校を10校から30校に拡大。志願者数35%増
- H大学:探究学習支援の成果を可視化し、県教育委員会との包括協定締結に成功
- I大学:高大連携活動のROIを明確化し、予算を2倍に増額。さらなる拡大へ
まとめ:戦略的パートナーシップが創る、大学の持続的成長
特定の高校から継続的に志願者が集まる大学には、偶然ではない戦略的な取り組みがあります。データに基づくターゲット校の選定、信頼関係構築の7つの黄金ルール、そして探究学習を軸とした実効性の高い連携プログラム。これらを組み合わせることで、大学は安定的な志願者確保と質の高い学生の獲得を実現できます。さらに、Study Valley TimeTactのようなデジタルツールを活用することで、限られたリソースで最大の効果を生み出すことが可能です。少子化が進む中、ターゲット校との戦略的パートナーシップは、大学の持続的成長を支える重要な柱となるでしょう。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。