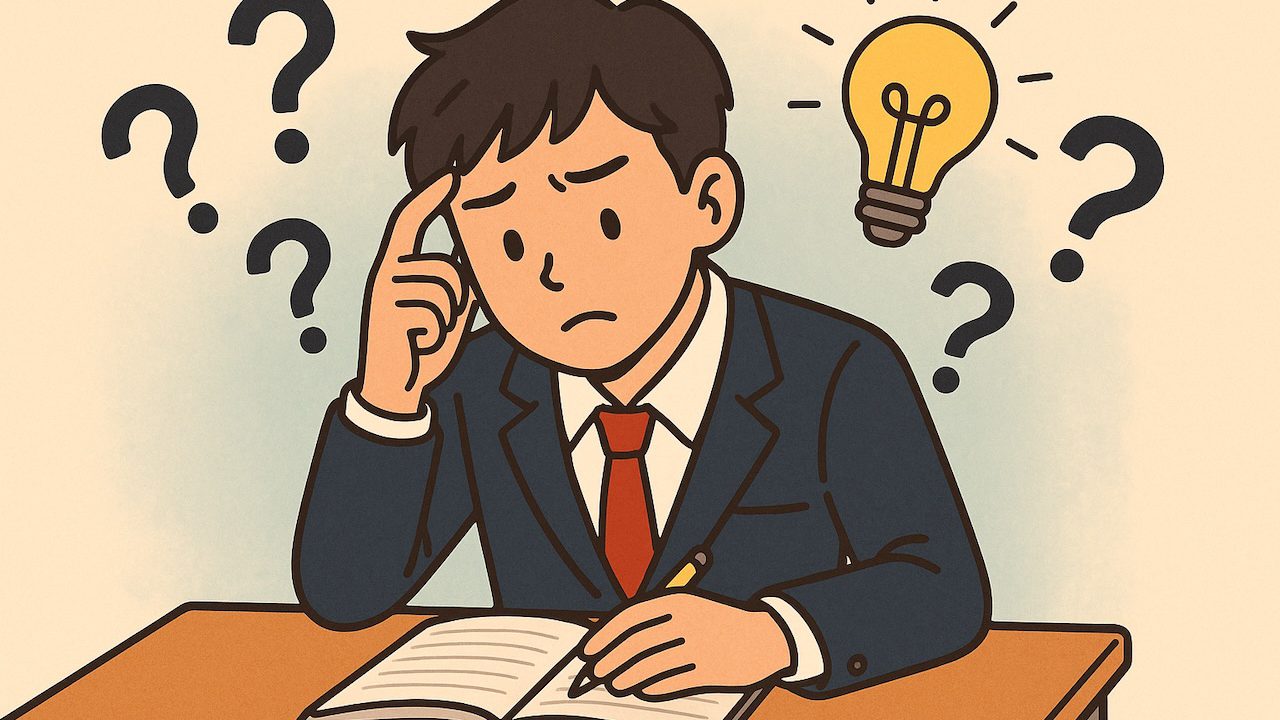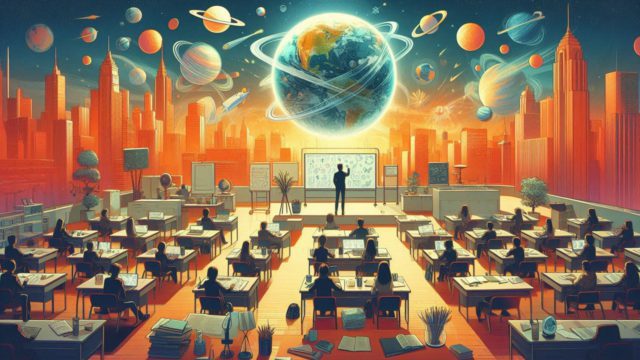「テーマが決まらない問題」を解決。生徒の知的好奇心に火をつける問いの立て方
探究学習の最初の関門として、多くの高校で「生徒がテーマを決められない」という課題に直面しています。「何でもいいから興味のあることを探究しなさい」と言われても、生徒は途方に暮れてしまうことが少なくありません。本記事では、この「テーマが決まらない問題」の本質的な原因を分析し、生徒の知的好奇心を喚起して主体的な探究へと導く「問いの立て方」について、具体的な手法とともに解説します。
 Screenshot
Screenshot 【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
なぜ生徒は探究テーマを決められないのか?
「テーマが決まらない」という状況には、複数の要因が絡み合っています。表面的には生徒の意欲や興味関心の問題のように見えますが、実際にはもっと構造的な課題が存在しています。
「正解」を求める思考の呪縛
従来の教科学習では、「正解のある問題」に取り組むことが中心でした。そのため、生徒は「良いテーマ」「正しいテーマ」を選ぼうとして身動きが取れなくなってしまいます。探究には正解がないという本質を理解できていないことが、最初のつまずきの原因となっています。
日常と学問の断絶
学校で学ぶ知識と日常生活での経験や疑問が結びついていないことも大きな要因です。「数学や理科は教科書の中の話」「社会問題は大人が考えること」といった認識があると、身の回りの事象から探究テーマを見出すことが困難になります。
「問い」を立てる経験の不足
これまでの学習経験の中で、自ら問いを立てる機会がほとんどなかった生徒が多いのが現実です。与えられた問題を解くことには慣れていても、問題そのものを発見したり設定したりする力が育っていないため、探究の出発点で躓いてしまいます。
知的好奇心を呼び覚ます「問いの種」の見つけ方
生徒が主体的に探究テーマを設定できるようになるためには、まず「問いの種」を見つけることから始める必要があります。以下、効果的なアプローチを紹介します。
1. 日常の「違和感」を言語化する
生徒に「最近、何か変だなと思ったことはない?」と問いかけることから始めます。例えば:
- 「なぜコンビニの商品配置はどの店も似ているのか」
- 「SNSで同じような投稿ばかり見るのはなぜか」
- 「学校の制服はなぜ必要なのか」
こうした日常の小さな違和感こそが、深い探究へと発展する可能性を秘めています。
2. 「もし〜だったら」思考実験
現実とは異なる状況を想像することで、新たな視点が生まれます:
- 「もし学校に試験がなかったら、どんな学びが可能になるか」
- 「もし地球の重力が半分になったら、社会はどう変わるか」
- 「もしお金という概念がなかったら、経済はどう成り立つか」
この手法は、既成概念から自由になり、創造的な問いを生み出す効果があります。
3. 身近な人の「困りごと」から始める
家族や友人、地域の人々が抱える課題に目を向けることで、社会的意義のある探究テーマが見つかります:
- 「祖父母がスマホを使いこなせない理由と解決策」
- 「部活動で怪我が多い原因と予防法」
- 「地元商店街の活性化に必要なこと」
「良い問い」の条件と磨き方
問いの種が見つかったら、それを探究に値する「良い問い」へと発展させる必要があります。良い問いには以下のような特徴があります。
開かれた問いであること
「Yes/No」で答えられる閉じた問いではなく、多様な視点や解釈が可能な開かれた問いが探究には適しています。例えば、「日本の出生率は低下しているか?」ではなく、「なぜ日本の若者は子どもを持つことに消極的なのか?」という問いの方が、探究の幅が広がります。
具体性と抽象性のバランス
あまりに抽象的すぎる問いは手がかりがつかめず、逆に具体的すぎると探究の広がりが制限されます。「なぜ私たちの学校の図書館利用者が減っているのか」のように、身近な具体例から普遍的な問題へと展開できる問いが理想的です。
探究者自身との関連性
生徒自身の経験や関心と結びついた問いは、探究への動機づけが持続しやすくなります。「なぜ私は〜なのか」「私たちの世代は〜についてどう考えているのか」といった、自分事として捉えられる要素を含むことが重要です。
教師が実践できる「問いづくり」支援の具体的手法
生徒が自力で問いを立てられるようになるまでには、教師による適切な支援が不可欠です。以下、実践的な指導法を紹介します。
1. ブレインストーミング・セッション
クラス全体で行う問いづくりワークショップ:
- テーマ(例:「学校」「SNS」「環境」)を提示
- そのテーマに関する疑問を制限時間内に書き出す
- グループで共有し、問いを分類・整理
- 興味深い問いを選んで深掘りする
この活動により、他者の視点から刺激を受け、自分では思いつかなかった問いに出会える効果があります。
2. 「Why階段」メソッド
一つの事象に対して「なぜ?」を繰り返すことで、問いを深化させる手法:
- 現象:「高校生の読書離れが進んでいる」
- Why1:なぜ高校生は本を読まなくなったのか?
- Why2:なぜスマホの方が魅力的なのか?
- Why3:なぜ即座に得られる情報を好むのか?
この過程で、表面的な問題から本質的な問いへと掘り下げることができます。
3. 問いの相互フィードバック
生徒同士で問いを評価し合う活動:
- 各自が立てた問いを発表
- 「興味深さ」「探究可能性」「独自性」の観点で相互評価
- フィードバックを基に問いを改善
この活動により、問いの質を客観的に判断する力が養われます。
Study Valley TimeTactで「問いづくり」をサポート
ここまで、生徒の知的好奇心を喚起し、探究テーマへと導く方法について解説してきました。しかし、全ての生徒に対して個別に問いづくりを支援することは、教師にとって大きな負担となります。そこで活用したいのが、Study Valley TimeTactです。
AIによる問いの提案機能
TimeTactは、生徒が入力したキーワードや興味関心から、探究に適した問いを複数提案します。単なるテーマ提示ではなく、その生徒の学習履歴や興味の傾向を分析し、パーソナライズされた問いを生成することで、生徒一人ひとりに最適な探究の出発点を提供します。
問いの深化を促す対話型サポート
チャットボット機能により、生徒の問いに対して「それはなぜ?」「具体的には?」といった問いかけを自動的に行います。これにより、教師が付きっきりでなくても、生徒は自分のペースで問いを深めていくことができます。
他校の優れた問いから学ぶ
TimeTactのプラットフォーム上では、他校の生徒が立てた優れた問いの事例を参照できます。同世代の生徒がどのような視点で問いを立てているかを知ることで、自分の問いづくりの参考にすることができます。
問いの質を可視化する評価機能
立てた問いの「探究可能性」「独自性」「社会的意義」などを自動評価し、改善のヒントを提供します。これにより、生徒は客観的な基準を持って自分の問いをブラッシュアップすることができます。
まとめ:問いを立てる力こそ、21世紀型スキルの核心
「テーマが決まらない問題」は、単に探究学習の導入部分の課題ではありません。自ら問いを立てる力は、変化の激しい社会を生き抜くための必須スキルです。AIが多くの問題を解決してくれる時代だからこそ、「何を問うべきか」を考える力の重要性はますます高まっています。
教師の皆様には、生徒が安心して「分からない」「不思議だ」と言える環境を作り、問いを立てることの楽しさと価値を伝えていただきたいと思います。そして、Study Valley TimeTactのようなツールを活用することで、より多くの生徒が自分だけの問いを見つけ、主体的な探究学習へと踏み出せることを願っています。問いを立てる力を育むことは、生徒の未来を拓く最も重要な教育の一つなのです。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。